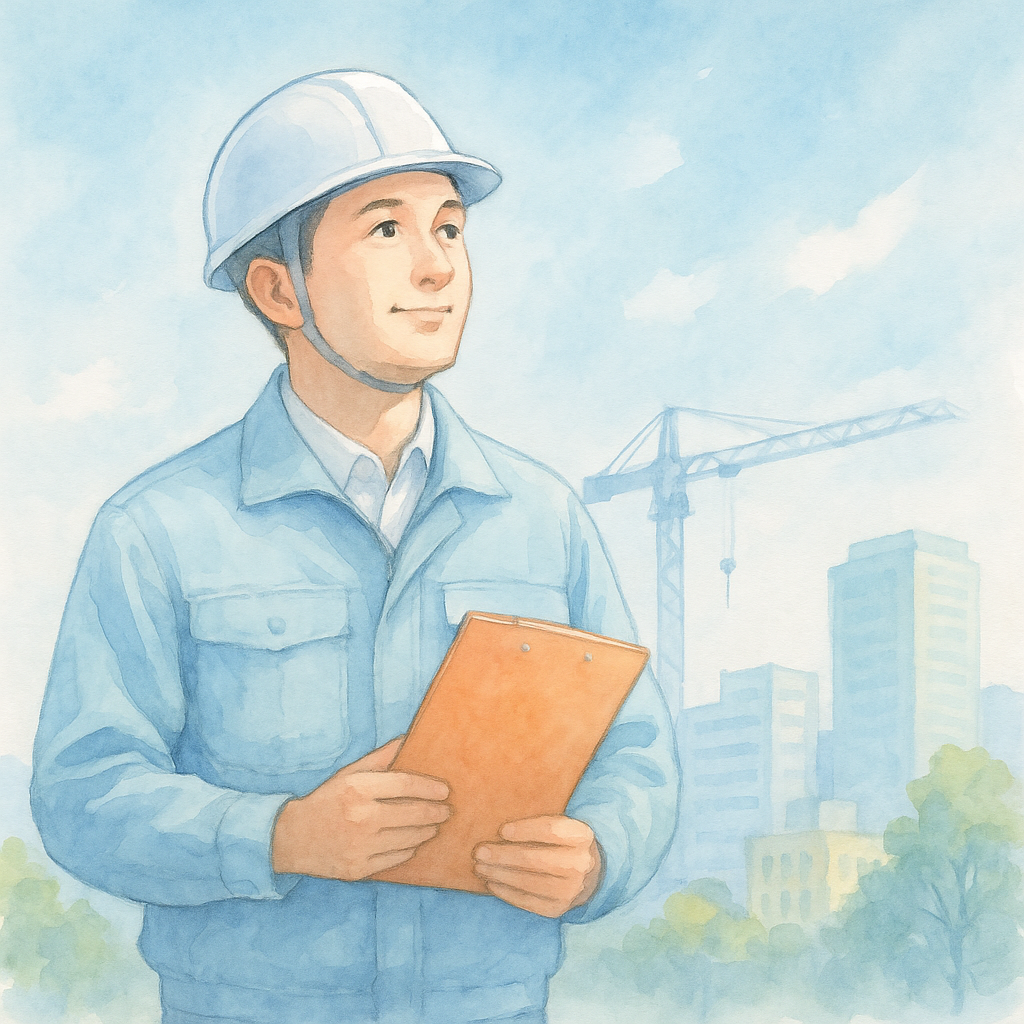目次
なぜ今、建設業の資金繰りが危ないのか
建設の現場で汗を流してきた経営者や職人の方々にとって、「倒産件数が増えている」というニュースは決して遠い話ではありません。帝国データバンクの発表によると、2025年上半期の建設業の倒産は 986件。これは過去10年間で最多の数字です。
「ウチは大丈夫だろう」と思いたい気持ちは分かります。しかし、この数字は決して他人事ではありません。むしろ、地域に根ざす中小の建設会社こそ直撃を受けやすいのが現実です。
かつてのリーマンショック時には、大手企業の倒産が話題になりました。ところが今は事情が違います。増えているのは 職別工事業や設備工事業などの比較的小規模な専門工事業者。つまり、地域密着で仕事を続けてきた会社が、資材高騰や人手不足の波にのまれているのです。
「腕はあるのに、人を確保できない」「工期が守れず外注費がかさむ」「支払いは先行するのに、入金は先延ばし」。そんな“現場あるある”が、倒産リスクに直結している現状が浮き彫りになっています。
さらに追い打ちをかけるのが、資金繰りの環境変化です。
政府は2026年度末までに「手形廃止」を目指しており、これまで当たり前のように使ってきた資金調達の仕組みが変わろうとしています。現金払いが進めば健全化という面もありますが、一方で「期日現金」と呼ばれる90日〜120日の長期支払いが増える懸念も。しかも現金払いは、手形のように「不渡り」がなく、むしろ回収リスクは高まる可能性もあるのです。
こうした背景を踏まえると、今の建設業経営者に求められるのは「景気が回復するのを待つ」姿勢ではなく、資金繰りそのものを戦略的に見直す姿勢です。
倒産件数が最多となった今だからこそ、資金の流れを改めて点検し、強い体質に変えていくことが生き残りのカギになります。
第2章 「現場で起きている資金繰りの“悪循環”」
「材料費の支払いは先に来るのに、工事代金の入金は後回し」。
建設業に携わる方なら、こうした資金繰りのズレに一度は悩まされたことがあるのではないでしょうか。
実際に今年、破産手続きに入った管工事業者のケースでは、まさにその典型的な悪循環が見られました。
人手不足で自社施工が追いつかず、外注費が増加。その一方で売上は減少傾向にあり、結果として資金がショートしてしまったのです。熟練職人の高齢化や若手不足が続く中、どの会社にも起こり得る話です。
さらに、2024年から適用が本格化した時間外労働の上限規制も影響しています。
「工期を短縮したいのに人を増やせない」「残業で乗り切ることもできない」。こうして工期は延び、外注比率が高まる。支払いが先行し、資金繰りはさらに苦しくなる。多くの現場で、同じような悪循環が繰り返されています。
とりわけ厳しいのは、住宅関連の専門工事業者です。新築着工数が減少するなか、資材や人件費の上昇分を価格に転嫁しにくい状況が続いています。元請からは「コストを抑えてほしい」と言われ、職人には「賃金を上げてほしい」と求められる。板挟みになった末に、キャッシュが回らなくなり、最悪の事態に至るケースが少なくありません。
加えて、従来の「手形による支払い」が廃止に向かっていることも、現場に不安を与えています。
「現金払いに移行すれば健全」と一見思えますが、実際には支払いサイトが長期化し、入金が遅れる懸念があります。しかも現金払いは、不渡りのような“ストッパー”がなく、回収リスクはむしろ高くなる可能性があるのです。
このように、資材価格高騰・人手不足・制度変更という“三重苦”が同時進行で進んでいるのが、今の建設業のリアルです。
「資金繰りが厳しいのはウチだけじゃない」という安心感は、むしろ危険信号かもしれません。業界全体で悪循環に陥っているからこそ、早めの対策が必要になります。
制度の変化を味方にできるかが分かれ道
資金繰りに影響を与えるのは、景気や物価の変動だけではありません。
建設業界を取り巻く制度の変更も、大きなターニングポイントになります。ここでは特に押さえておきたいポイントを整理してみましょう。
手形廃止と現金払いへの移行
政府は2026年度末をめどに、商取引での手形利用を廃止する方針を打ち出しました。
これまで建設業界では「手形」が資金繰りの命綱として機能してきました。資材購入や外注費の支払いを手形でつなぎ、工事代金の入金を待つ。この流れが一般的でした。
しかし今後は「期日現金」での支払いが主流に移行していきます。
現金払いなら資金の健全化につながる面もありますが、実際には 90日〜120日の長期サイト が設定されるケースも多く、入金の遅延リスクはむしろ高まる可能性があります。資金繰り表をきちんとつけ、入出金のタイムラグを見える化することが、ますます欠かせなくなります。
経営事項審査(経審)の重要性
公共工事の入札に参加する企業にとって、「経営事項審査(経審)」は避けて通れません。
経審では財務内容や経営状況が点数化され、入札の可否や格付けに直結します。特に資金繰りが厳しくなると、自己資本比率が低下し、点数にマイナス影響が出やすくなります。
「資金がショートしそうだから、とりあえず借り入れで凌ぐ」だけでは、経審の点数が下がり、公共工事の受注機会を失うリスクがあります。資金調達と同時に 経審の点数維持を意識した財務改善 が求められるのです。
資金調達の選択肢
中小建設業が頼りにしてきた金融支援も、コロナ禍の特例融資が終わり、返済負担が増してきています。加えて金利の上昇傾向も無視できません。
その中で注目されるのが、補助金や助成金の活用です。例えば、生産性向上や省エネ化に関する補助金をうまく使えば、資金繰りを圧迫する投資を軽減できます。
また、自治体独自の融資制度や保証協会付き融資を利用すれば、民間金融機関より有利な条件で借りられる場合もあります。単に資金を借りるだけでなく、制度を比較検討する目を持つことが、今後は生き残りの条件になります。
明日からできる資金繰り改善のステップ
制度の知識を押さえたうえで大切なのは、実際に自社の経営に落とし込むことです。資金繰りの悪循環を断ち切るために、現場の建設業者が取り組める具体的な行動を整理します。
1. 資金繰り表を“動かす”こと
資金繰り表を作っただけで終わっていませんか?
毎月の入金・支出を更新し、90日先までの資金の動きを確認しておくと「いつ資金が不足するか」を事前に把握できます。特に現金払いの比率が増えている今、資金繰り表は経営の羅針盤になります。Excelや会計ソフトに標準機能があるので、小規模な会社でも十分対応可能です。
2. 入金サイトを短縮する交渉
「元請だから仕方ない」とあきらめる前に、支払い条件を見直す交渉を試みることも重要です。
最近では建設キャリアアップシステム(CCUS)の普及により、下請や職人への支払いを早める取り組みが進んでいます。自社も積極的に活用し、できる限り入金サイトを短くすることがキャッシュフロー改善の第一歩になります。
3. 補助金・助成金を事業に組み込む
資材の高騰や省エネ対応のための設備投資は、補助金を活用できる分野です。
「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」「省エネ補助金」などは建設業者の活用例も多く、調達した資金の返済負担を軽減できます。さらに自治体独自の補助金も見逃せません。自社の強みや課題に合わせて制度を選ぶ工夫が求められます。
4. 借入は「安く長く」を基本に
短期の借入で急場をしのぐのではなく、長期借入で安定した返済計画を立てることが望ましいです。保証協会の制度融資や自治体のセーフティネット保証などを利用すれば、金利を抑えつつ借入期間を延ばせるケースがあります。
「返せるか不安だから借りない」ではなく、リスクが高まる前に余裕を持って調達するのがポイントです。
5. 経審・建設業許可を意識した財務改善
公共工事を狙う会社なら、資金繰りの安定は経営事項審査の点数にも直結します。自己資本比率や利益率を少しでも改善できれば、点数アップと資金調達力の向上の両方に効果があります。
経審対策と資金繰り対策は切り離せるものではなく、両輪で進めることが生き残りの条件です。
資金繰りを見直すことが、未来を守る第一歩
2025年上半期の倒産件数は986件。過去10年間で最多という数字は、建設業界にとって無視できないシグナルです。
資材高騰や人手不足、そして制度の変化――これらは避けて通れない現実です。けれども、ここで立ち止まるか、資金繰りを戦略的に見直すかで、これからの会社の未来は大きく変わっていきます。
「資金繰り表なんて難しい」「補助金は手続きが面倒」「経審の点数は意識したことがない」――そんな声もよく耳にします。ですが、資金繰りを放置したままでは、気づいたときには手遅れになりかねません。
逆に言えば、今から取り組めば間に合うのです。
- 入出金のタイムラグを“見える化”する
- 支払い条件の見直しを試みる
- 補助金・制度融資を調べてみる
- 経審や許可を意識した財務改善に一歩踏み出す
どれも今日からできる行動です。小さな取り組みが積み重なり、やがては会社の体質を強くしていきます。
もし「どこから手をつけたらいいか分からない」と迷うなら、専門家に相談してみるのも一つの方法です。建設業許可や経営事項審査、資金調達に詳しい実務者であれば、現場の事情に即したアドバイスが得られるはずです。
地域で頑張る中小建設業がなくなってしまっては、暮らしの基盤を守ることはできません。だからこそ、資金繰りの見直しは「自社のため」だけでなく「地域の未来のため」でもあります。
このタイミングで一歩踏み出すことが、あなたの会社と仲間を守ることにつながります。