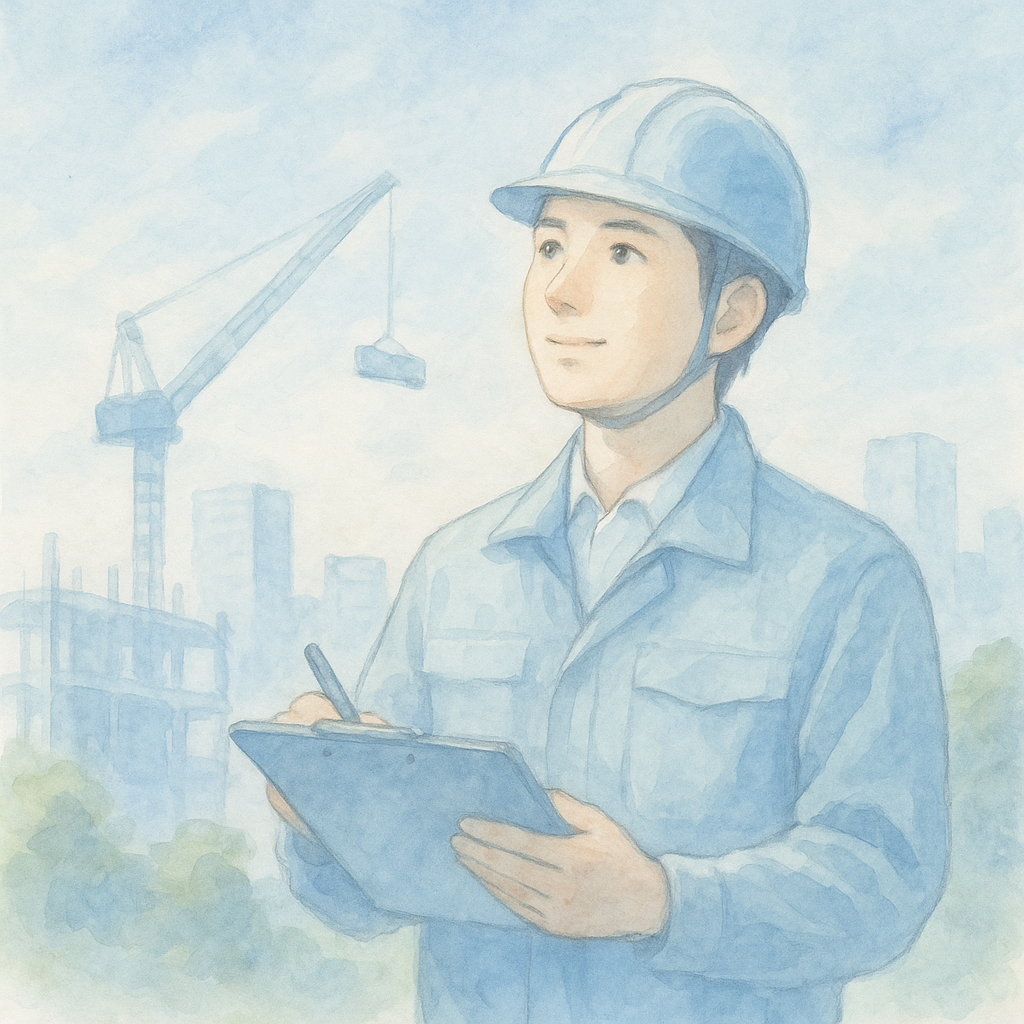目次
技術職員が減る時代に、建設業の経営はどう変わる?
「昔に比べて、役所の窓口での打ち合わせがスムーズにいかなくなった」
「設計変更や工期の相談で、専門的な話が通じにくいことが増えた」
そんな声を、建設業の経営者や現場監督の方からよく耳にします。背景には、自治体の“土木技師不足”があります。実際、1997年度に約3.9万人いた都道府県の土木技師は、2023年度には2.9万人まで減少。中には、技術職員が一人もいない自治体が全国で449団体にのぼるというデータも出ています。
こうした状況は、インフラの整備や維持管理だけでなく、建設会社に直接的な影響を及ぼしています。役所側の技術チェックが手薄になれば、工事発注や検査の進み方が変わる。結果として、建設業許可や経営事項審査の評価、さらには補助金・資金調達の場面にまで影響が及ぶケースも少なくありません。
本記事では、「建設業 × 実務支援」という視点から、制度や経営に関わるリスクとその備え方をわかりやすく整理していきます。現場の経営者や後継者候補の方が、「いま何をすればいいのか」を考えるきっかけになるよう、具体的な行動のヒントまでお伝えします。
「役所に技術者がいない」ことで起きている現場の困惑
現場で働く方なら、一度はこんな経験をしたことがあるのではないでしょうか。
- 発注者の担当者が土木の専門知識を持っておらず、設計変更の説明が何度も必要になった
- 工事費の積算や監督検査に時間がかかり、工期の調整が難航した
- 入札に関する相談をしても「判断に時間がかかる」と言われ、意思決定が遅れた
こうした背景には、自治体の土木技師不足があります。総務省の調査によると、役場に土木技師が一人もいない自治体が全国で 449団体。小規模な町や村では、事務職員が土木系の案件を担当せざるを得ないケースが増えているのが現状です。
特に困るのは、工事の品質や安全性に直結する場面です。本来なら技術職員が確認すべき設計や仕様を、専門知識が不十分なまま承認せざるを得ない。結果として、施工業者に「役所が何を求めているのか」が伝わりにくくなり、現場と発注者との間で認識のズレが生じやすくなります。
さらに、この流れは 建設業許可や経営事項審査の実務 にも波及します。たとえば、技術職員が不足している自治体では、入札契約の適正化や週休2日モデル工事といった新しい制度の導入が遅れる傾向があります。つまり、制度に正しく対応している建設会社であっても、そのメリットを十分に享受できない状況が生まれるかもしれないということです。
こうした「制度の遅れ」「判断の遅れ」「技術確認の遅れ」が重なると、最終的に影響を受けるのは施工を担う建設会社側です。資金繰りや労務管理に直結するだけに、経営者や後継者にとっては見過ごせないリスクとなっています。
建設業許可・経営事項審査・資金調達に広がる影響とは
「役所に技術職員がいない」という状況は、実は建設業の制度面にも少なからず影響しています。ここでは、代表的な3つの制度との関わりを整理します。
建設業許可:更新や要件確認の遅れ
建設業許可を持つ会社にとって、更新忘れは致命傷になりかねません。ところが、自治体の担当部署に技術者が不足していると、申請内容の確認や相談対応に時間がかかることがあります。結果として、申請手続きがギリギリになったり、書類の不備を直す余裕がなくなるリスクがあります。
特に中小建設業者では、専任技術者や経営業務管理責任者の配置要件をクリアすること自体が経営課題となりやすいため、窓口対応の遅れは直接的な痛手になりかねません。
経営事項審査(経審):自治体の評価作業にも影響
公共工事を受注するためには避けて通れないのが経営事項審査。経審は「経営規模」「技術力」「社会性」などを点数化し、その合計で競争力が左右されます。
ここでも、技術職員の不足が影を落としています。自治体によっては、審査の担当者が事務職であり、建設業の実情を十分に把握していないため、審査過程での問い合わせが多くなる傾向があります。その結果、審査結果が出るまでに想定以上の時間を要し、入札に間に合わないという事例も散見されます。
資金調達支援・補助金:制度導入の地域差
さらに、建設業界の経営に直結するのが資金調達や補助金制度です。国交省が進める「施工時期の平準化」や「週休2日モデル工事」といった新しい取り組みは、金融機関や補助金審査でも評価ポイントになりやすい分野です。
しかし、小規模自治体では導入が遅れており、事業者が制度の恩恵を受けにくい状況があります。つまり、同じ制度でも「地域によってチャンスに差が出る」という格差が生じてしまうのです。
このように、土木技師不足という一見「役所側の問題」に見えるテーマは、建設会社の許可・審査・資金調達という経営の根幹に波及しています。だからこそ、制度の“待ち”の姿勢ではなく、経営者側から積極的にリスク回避の備えを取っていくことが欠かせません。
今すぐできる“備え”と実務のチェックポイント
制度や環境の変化は待ってくれません。技術職員不足という外部要因に振り回されないためには、建設会社自身が「できることから備える」姿勢が大切です。ここでは、すぐに実践できる行動のヒントを整理します。
1. 建設業許可・更新は“前倒しスケジュール”で
申請や更新は、ギリギリではなく余裕をもって着手することが鉄則です。
- 更新期限の半年前から必要書類を洗い出す
- 専任技術者や経営業務管理責任者の配置要件を確認する
- 不測の指摘や差し戻しに備えて「バッファ期間」を設定する
これだけでも、役所対応の遅れに左右されるリスクを大幅に減らせます。
2. 経営事項審査(経審)の評価項目を“逆算”して準備
経審は単なる申請作業ではなく、日常的な経営管理の積み重ねが点数に直結します。
- 技術職員の資格取得や配置状況を定期的にチェック
- 社会保険加入や法令遵守状況を社内で記録・整備
- 点数アップにつながる経営改善(利益率・自己資本比率の強化)を計画的に進める
「入札に必要だから仕方なく」ではなく、「点数を活かして受注を拡大する」姿勢で臨むと、審査準備が経営強化にもつながります。
3. 資金調達・補助金は“情報格差”を埋める
小規模自治体では制度導入が遅れることがありますが、逆に国や都道府県レベルでの補助金・助成金には積極的にアクセスできます。
- 中小企業庁や国交省の最新施策を定期的に確認
- 金融機関や商工会議所のセミナーに参加し、評価される取り組みを把握
- 補助金申請は単発でなく「次年度も見据えて継続活用」する
情報を先取りできれば、地域差による不利をある程度カバーすることが可能です。
4. 外部専門家を“味方”につける
制度や書類の複雑さに追われて本業の工事に支障が出てしまっては本末転倒です。
- 建設業許可や経審に強い行政書士に相談する
- 会計・資金繰りは税理士や金融機関と連携する
- 技術職員不足の自治体とやり取りする際の“橋渡し役”を確保する
経営者がすべてを抱え込むのではなく、専門家を上手に活用することでスピード感と安心感を確保できます。
技術者不足という大きな流れは、会社単独で変えられるものではありません。だからこそ「制度対応を前倒し」「情報格差を埋める」「外部リソースを活用する」という3つの備えが、経営を安定させる鍵となります。
「備え」を行動に変えて、会社を次のステージへ
いま、地方自治体で進んでいる技術職員の減少は、決して遠い世界の話ではありません。
役所の対応が遅れる、制度導入が進まない――そのしわ寄せは、最終的に現場を支える建設会社に及びます。
だからこそ、待つのではなく、自ら備えることが大切です。
- 許可や経審は「前倒し」で準備する
- 評価項目を逆算し、経営改善につなげる
- 補助金や資金調達は「情報格差」を埋める意識で動く
- 専門家を味方につけ、制度の橋渡しを任せる
こうした小さな積み重ねが、会社の安定と次の受注につながっていきます。
「役所が変わるのを待つ」のではなく、「自社が動ける範囲で一歩踏み出す」。その積極的な姿勢が、技術者不足時代を生き抜く最大の武器になるはずです。
もし「自分の会社はどこから手を付ければいいのか分からない」と感じたら、行政書士などの専門家に気軽に相談してみてください。制度の細かい要件や手続きの流れを整理してもらうだけでも、経営者としての判断がぐっと楽になります。
未来の現場を支えるのは、いま備えを始めた会社です。今日からできる一歩を踏み出してみませんか。