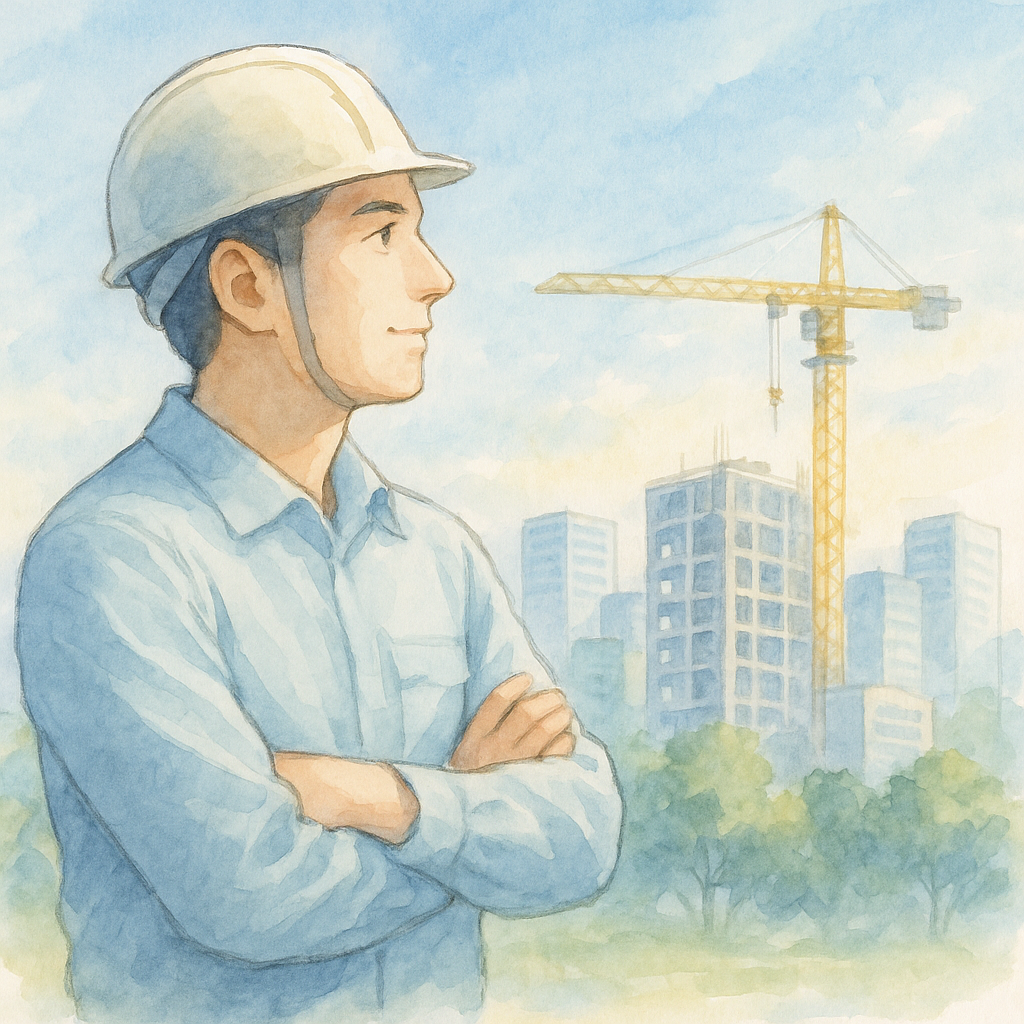目次
「年度末が勝負」はもう古い?建設現場の“波”に振り回されていませんか
「3月に工事が集中して忙殺された」
「4月〜6月は仕事が減って、職人の手配にも困った」
──これは、市川市内の中小建設業者からよく耳にする声です。
公共工事の施工時期には、いわゆる“繁閑の波”があります。とくに年度末の1〜3月は多くの自治体が予算消化のために工事を発注し、現場が立て込む傾向にあります。その一方で、年度初めの4〜6月は工事の稼働が極端に減る「閑散期」となりがちです。
こうした波に振り回されると、以下のような問題が現場にのしかかります。
- 冬場の厳しい気候条件での無理な工期消化
- 繁忙期の人手・資材不足によるコスト高騰
- 閑散期の売上減による資金繰り不安
事業計画も立てにくく、急な応札や慌ただしい現場対応で、品質や安全にまで影響が出かねません。とくに近年は物価高騰や人件費の上昇も重なり、こうした「波」が経営リスクに直結するようになっています。
ところが今、国がこの“波”を平準化する方向に大きく舵を切りはじめました。
そしてその動きは、私たちのような地場建設業者にとって、大きなチャンスにもなりうるのです。
次章では、「施工時期の波」を可視化する新しい指標や、奈良や福岡で実際に起きている現場の実情をご紹介します。
工事の“波”が見える化される?国の新制度が現場にもたらすインパクト
「工事がいつ集中して、いつ少ないのか」──これは経験や勘だけではなく、今や“数値”で可視化できる時代になりつつあります。
2024年6月、国土交通省は改正された公共工事品質確保促進法(通称:品確法)に基づき、新しい平準化の評価指標「第3次全国統一指標」の運用を開始しました。
この新指標では、これまで4〜6月(年度初め)の稼働状況だけを対象としていたところに、1〜3月(年度末)も加えて、年間を通じた「施工時期の波」を把握できるようになっています。
具体的には、以下の2つの数値で構成されます。
- 春の閑散期(4〜6月)の稼働率
- 冬の繁忙期(1〜3月)の稼働率
これを県単位・地域ブロック単位で可視化し、各地域の「波の大きさ」を見比べることが可能に。たとえば、2023年度の実績では、奈良県や福岡県ではこの波が特に大きいことが明らかになっています。
では、千葉県はどうか?
とくに市川市のような都市近郊エリアでは、年度末に向けた駆け込み発注や、周辺自治体の動向に左右されやすい傾向があります。さらに都心からのアクセスもよく、近隣自治体の繁忙が市川に波及するケースも。
こうしたなか、新しい制度は「自社の工期の平準化」を促すだけではありません。
市川市内の発注元(県・市・公共団体)もまた、この指標を見ながら「繁忙期のピークカット」「閑散期の底上げ」に取り組むよう求められるのです。
言い換えれば、平準化に前向きな事業者ほど、今後の公共工事で有利に働く可能性があるということ。
次章では、国交省が提唱する「さしすせそ」の具体策や、現場でできる対応をわかりやすく整理していきます。
“さしすせそ”って何?制度を味方につけるためのヒント
制度の動きをただ「見ているだけ」では、建設会社の未来は変わりません。
むしろ、制度の意図を読み解き、先回りして動いた会社こそが、今後の発注や評価で優位に立つことになります。
では、具体的にどう動けばよいのでしょうか。
国土交通省は、工期の平準化を現場で実現するために、覚えやすい合言葉を用意しています。
それが「さ・し・す・せ・そ」。
これは単なる語呂合わせではなく、建設業者と発注者が一緒に意識すべき5つの実務対策をまとめたものです。
✅ 債務負担行為の活用(さ)
翌年度にわたる工事に対応するための予算措置。これにより、3月末で予算が切れる“駆け込み発注”を減らし、余裕のある工期設定が可能に。
✅ 柔軟な工期設定〈余裕期間制度の活用〉(し)
天候や資材調達の事情に応じた柔軟なスケジュール管理を可能に。繁忙期でなくとも対応しやすくなるため、工事を閑散期に回しやすくなります。
✅ 速やかな繰り越し手続き(す)
予期せぬ事情で工事が年度内に完了しない場合、速やかに翌年度に繰り越すことで、余計な焦りや損失を避けることができます。
✅ 積算の前倒し(せ)
設計・積算を早めに行うことで、年度初めから工事を始められるように。4月からの稼働率向上=閑散期の底上げに直結します。
✅ 早期執行の目標設定(そ)
発注者側が明確な目標を持って早めに執行することで、事業者側も計画的に動けるように。結果的に“波”が小さくなり、無理のない受注が可能に。
これらの施策は、発注者だけがやることではありません。
むしろ、事業者側が「自社の体制を整える」ことで、上記のような制度の活用を“引き出す”ことができるのです。
たとえば――
- 年度初めにすぐ対応できるよう、設計・積算・協力会社との連携体制を準備しておく
- 閑散期でも受注できるように資金繰りや工程計画に余裕を持たせる
- 工期の柔軟な交渉ができるよう、信頼関係のある取引先を維持する
こうした地道な取り組みが、長期的には「評価の高い業者」として選ばれる道につながります。
次章では、市川市でこうした変化を“チャンス”に変えるための具体的な行動や備え方をご紹介します。
“波”を味方にする経営術──市川の建設会社が今すぐできる3つの備え
制度が変わったからといって、すぐに発注時期が整うわけではありません。
でも、波があるなら“その波に乗る”方法を考えたほうが、確実に前に進めます。
ここでは、市川市の中小建設業者が実際に取り組める3つの備えをご紹介します。
① 閑散期の工事受注に向けた「資金繰りの余裕づくり」
4〜6月は工事が減る…だからといって、黙って待つ必要はありません。
この時期に稼働できる工事があると、実はライバルが少ない=採算が良いというメリットもあります。
しかし、閑散期に動けるかどうかは「資金繰り」がカギになります。
たとえば…
- 売上が減る時期に備えて、前年度から借入枠を確保しておく
- 小規模事業者持続化補助金や、建設業者向けの制度融資を利用する
- 支払サイトの見直しや、材料仕入れのキャッシュフローを再検討する
「余裕資金がある=チャンスをつかめる力がある」
この構えがあるだけで、発注側からの評価も変わります。
② 公共工事向けの「経審対策」を早めに
工事が春から動くとしたら、経営事項審査(経審)の評価タイミングにも注意が必要です。
毎年の申請を“例年通りの時期”にしていませんか?
でも実は、審査のタイミング次第で、受注できる工事に差がつくことがあります。
とくに「新年度スタートダッシュ」に乗るには、早めの経審取得や入札参加資格の更新が不可欠。
加えて、以下のようなスコアアップ策も見直しておきましょう。
- 技術者の専任状況を明確にし、加点の対象に
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)登録者数の拡充
- 労働福祉の取り組み(健康診断、退職金共済など)の充実
制度の変更に合わせて、経審の中身もじわじわ変わってきているため、放置はリスクになりかねません。
③ 「現場が動ける季節」を意識した工事計画と人員戦略
市川市は降雪が少なく、冬場の施工も比較的しやすい地域です。
この地の強みを活かし、ピークシーズン(1〜3月)に偏らない受注・施工体制を整えることも大切です。
たとえば…
- 秋口からの設計・見積対応で、早期発注の工事に備える
- 冬季工事対応の職人スケジュールや防寒対策を事前に計画
- 協力会社との施工時期調整を年単位で打ち合わせる
現場レベルでのスケジューリングが整っていれば、発注者側も安心して早期発注や閑散期発注を相談できます。
小さな準備の積み重ねが、いつしか「選ばれる会社」へとつながる。
制度の波を嘆くのではなく、味方に変える動きこそが、これからの実務に求められています。
次章では、この記事全体を振り返りながら、建設会社としてどう動くべきか、やさしく背中を押すまとめをお届けします。
“波を読む力”が未来を変える──制度の波に乗るための次の一歩
建設業界には、自然と制度、そして経済の“波”があります。
それは市川市のような地域においても例外ではありません。
しかし、「波に振り回される側」から「波を読んで乗りこなす側」へとシフトできるかどうかが、今後の経営の分かれ道になります。
本記事では、以下のような流れでお伝えしてきました。
- 現場が抱える施工時期の偏りによるリスク
- 国の制度が“波の可視化”に動き出した背景
- 「さしすせそ」という実務的な制度対応策
- 市川市の中小建設業者ができる具体的な備え
こうした情報を「知って終わり」にせず、現場で活かすことが重要です。
🔹「制度に強い会社」=「選ばれる会社」へ
公共工事においては、ただ技術があるだけではなく、制度や仕組みを理解し、活用できる力が問われるようになっています。
- 閑散期にも工事を回せる資金計画がある
- 経審や入札対応が前倒しで整っている
- 施工体制が柔軟で、時期の波に対応できる
これらはすべて、制度の“使いこなし力”といえるでしょう。
🔹 専門家の伴走で、制度活用はもっと身近に
工事や経審、入札、補助金、資金繰りなど、制度は複雑に見えても、「現場目線」で翻訳してくれる伴走者がいれば、ずっとシンプルになります。
実際、私たちは市川市内を中心に、建設業の実務を支える支援者として、こうした制度の「翻訳」と「実装」をお手伝いしています。
- 更新手続きや経審対策の段取り
- 補助金・融資の申請サポート
- 資金繰りの事前準備と顧問的な継続支援
とくに制度の動きが変わりつつある今こそ、情報を「行動」に変えるチャンスです。
🔹 まずは気軽に話してみませんか?
「これってウチに関係あるの?」
「何から手をつけたらいいの?」
そう感じた方にこそ、話してほしいテーマです。
まずは一度、お話を聞かせてください。
あなたの現場に合わせた具体的なアドバイスを、制度にも現場にも通じた専門家がお届けします。
“波を読む力”があれば、経営はもっと穏やかに、もっと強くなります。