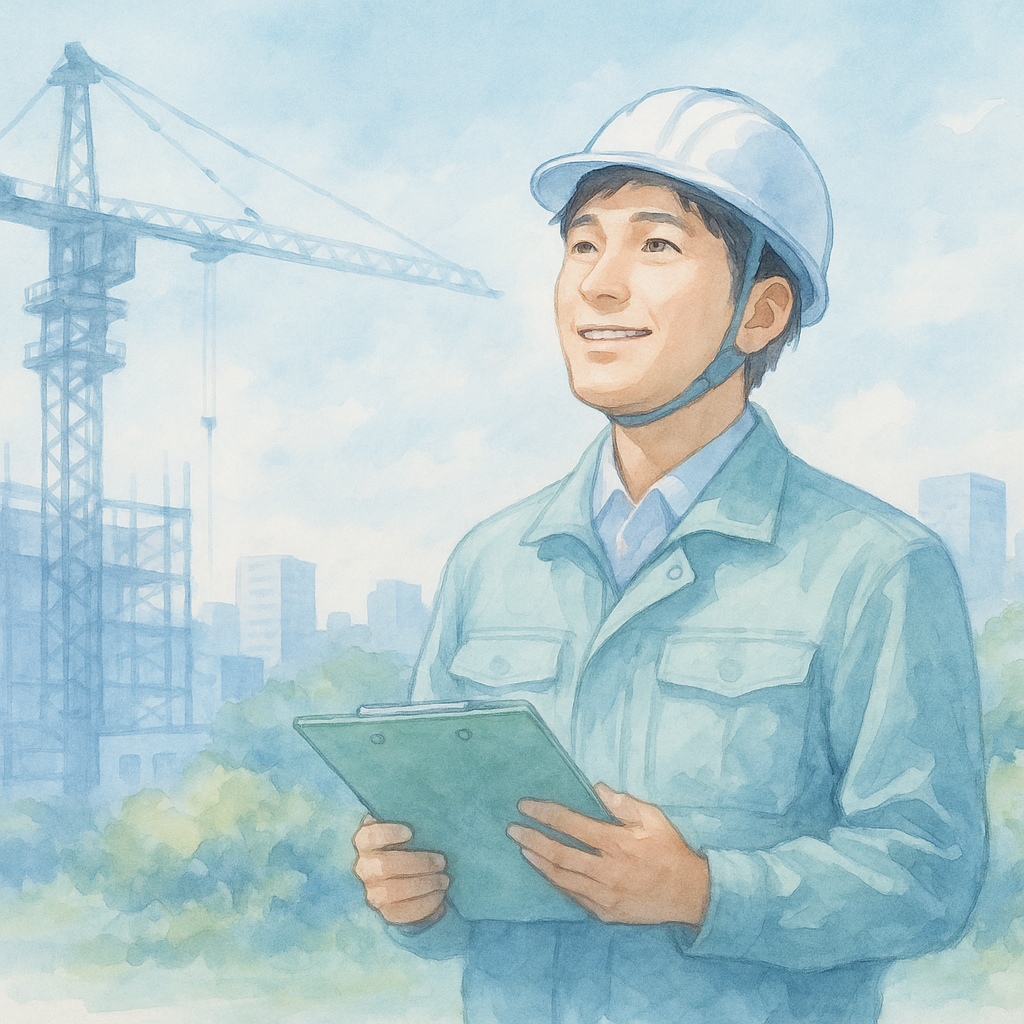目次
「また新しい制度?でも、正直よくわからない…」そんな声が聞こえる現場から
建設業を営んでいると、「制度がまた変わった」「国交省が新しい方式を始めた」といった話を耳にする機会が増えましたよね。でも、現場の声として多いのは、「結局、俺たちにはどう関係あるの?」という疑問ではないでしょうか。
今回ご紹介する「技術提案評価SI型(エスアイがた)」も、そのひとつ。2024年5月から国土交通省が試行を開始した新しい発注方式です。「省人化」「脱炭素」「安全性」といったキーワードが並びますが、それが自分たちの仕事や経営にどう影響するのか――実感を持てていない方が大半だと思います。
しかしこの「SI型」、決して一部の大手だけの話ではありません。むしろ、市川市のように中小企業が中心となって街を支える地域こそ、この制度の本当の恩恵を受けられる可能性があるのです。
なぜなら、SI型は「現場からの技術提案を正当に評価し、価格以外の価値で勝負できる」制度だからです。これまで埋もれてきた中小企業の技術力や工夫が、適切に評価されるチャンスとも言えます。
とはいえ、「そもそもどういう制度なの?」「提案書ってどう書くの?」「コストかかるんじゃないの?」といった不安もあるはず。
そこで今回は、市川市を拠点に建設業界の実務支援を行っている立場から、「SI型発注方式」について、現場にやさしく、制度にも詳しく解説していきます。
あなたの技術や工夫が、次の現場で“選ばれる理由”になるかもしれません。今こそ、制度の波をチャンスに変えていきましょう。
「あの会社は何で選ばれたの?」市川の中小建設業者が感じる“見えない壁”
市川市内で、ある公共工事の入札に挑戦した地元の建設会社。その社長がぽつりとこぼした言葉がありました。
「うちは実績もあるし、コストも抑えた。でも落ちた。選ばれたのは、聞いたこともない会社だったんだよな…」
これは決して珍しい話ではありません。むしろ、近年は「実力やコストだけでは選ばれない」ケースが増えているのが実情です。そこには、新しい選定基準=総合評価方式の影響があるのです。
とくに注目されているのが、「脱炭素」や「省人化」といった社会的要請に対応できているかという視点。つまり、「安い」よりも「持続可能で安全な施工ができる会社」が選ばれる時代になってきているのです。
しかし――。
そうした変化に対応するには、制度を理解し、技術提案書を作り、必要に応じて自社のやり方をアップデートしていかなければなりません。これが、中小企業にとっては非常に大きな壁です。
- 「書類が複雑すぎて、手が止まる」
- 「脱炭素って言われても、具体的に何をすればいいかわからない」
- 「結局、大手しか対応できないような制度なんじゃ…?」
そうした声も、日々の相談で多く寄せられます。
けれども、本当に必要なのは“完璧な技術力”ではなく、“自社の工夫や強みをきちんと提案する視点”です。たとえば、地域密着だからこそ可能な交通規制の工夫や、小規模事業者ならではの柔軟な工程管理も、SI型制度では評価対象になります。
つまり、「見えない壁」に見えていたのは、実は「提案の仕方」の問題だったのかもしれません。
次章では、この“SI型”がどんな仕組みで成り立っているのかを、専門用語を噛み砕いて解説します。
「制度が難しい」と感じている方も、安心して読み進めてください。
「技術提案評価SI型」って何?現場目線でわかる制度のポイント
新たに試行が始まった「技術提案評価SI型(エスアイがた)」――名前からして難しそうですが、実は、建設業者の“工夫”や“強み”を発注側がきちんと評価する制度です。
💡ざっくり言うと、どんな制度?
従来の公共工事では、「決められた設計図通りにやってください」が基本でした。でもこれだと、現場で「こっちのやり方の方が省人化できる」「もっと安全にできる工法がある」と思っても、なかなか提案の余地がありませんでした。
SI型は、その常識を変えます。
- ✅【目的物や仮設・工法】などを軽微に変更できる技術提案を認める
- ✅ 発注価格の最大5%までの範囲で設計変更を許容
- ✅ 評価基準には「脱炭素・安全性・工期短縮・維持管理性」などが含まれる
つまり、「うちはこんな工法がある」「この機材なら省人化・脱炭素にもなる」といった提案が評価され、受注につながる可能性が出てきたというわけです。
🛠 現場の工夫が“評価される時代”へ
たとえば以下のような現場改善の提案も、SI型では「技術向上提案」として正式に評価されます。
- ドローンやロボットによる無人施工
- CO₂排出量の少ない資材・重機の活用
- 点検が難しい箇所をメンテナンスしやすくする構造設計
- 作業員の安全性を高める現場配置や段取り
しかも、ただの「資材の置き換え」はNGですが、「自社で開発した独自技術」や「国交省の脱炭素アクションプランに沿った資機材」は、しっかり評価対象になります。
💰 お金と手間はどうなる?
受注側の負担を考慮し、提案にかかる費用(設計変更による増加分)は、予定価格の5%を上限に見積もり対応可能。つまり、「予算がないから提案できない」という心配も軽減されています。
また、技術提案の評価点は、全体の2分の1〜3分の1の配点。つまり、これまでより「提案内容そのものが合否を左右する」重要なカギになってきます。
「でも、どうやって自社の提案を考えればいいの?」
次章では、市川市の中小建設業者がこのSI型にどう備えていけばいいのか――具体的な行動のヒントをお届けします。
“制度を使いこなす中小企業”になるための3つの準備
「SI型、良さそうなのはわかったけど…結局ウチは何から始めればいいの?」
そんな声にお応えして、ここでは市川市の中小建設業者が今すぐ取り組める3つのステップをご紹介します。
①「自社の強み=現場の工夫」を“言語化”しておく
SI型では、「技術提案書」が評価のカギになります。
でも、提案書といっても、難しい技術論文を書くわけではありません。大切なのは、「なぜこの方法が省人化・安全につながるのか」を誰にでもわかる言葉で伝えることです。
たとえば…
- 「〇〇という手順を導入したら、作業員の負担が3割減った」
- 「この配置に変えたら、交通誘導が不要になり事故のリスクが減った」
こうした“日々の工夫”こそが、まさに技術提案のネタになります。
今のうちから、社内で「ウチの現場ならではの工夫」をストックしておくと、いざというときに役立ちます。
②「制度のポイント」を押さえるパートナーを持つ
制度の要件や評価基準は、正直かなり複雑です。建設業法や補助金の実務に強い専門家と連携しながら、“通る提案書”を効率よく作る体制をつくることが、最大の近道になります。
市川市内であれば、建設業支援に強い専門事務所も増えてきました。
行政手続・財務支援・BCP(事業継続計画)など、幅広くサポートできるパートナーに事前相談することをおすすめします。
③「制度を活かすタイミング」を見極める
SI型はまだ“試行”段階ですが、今後は地方自治体や他工種にも広がることが予想されます。情報収集を怠らず、次のような動きが出たらアンテナを立てましょう。
- 「総合評価型で技術提案を求める公告が出た」
- 「省人化・脱炭素を重視する補助金・入札案件が増えた」
- 「市川市や千葉県でSI型に類似したモデル事業が動き出した」
このような流れの中で、“今がチャンス”というタイミングを逃さないことが重要です。
中小企業だからこそできる現場提案が、これからの公共工事では「選ばれる理由」になります。
それを言語化し、制度とつなげる力を持つことが、次の時代の経営力です。
次章では、これまでの内容を振り返りつつ、「明日からできる一歩」をやさしく提案します。
制度の波にのまれない、“選ばれる企業”への第一歩を
ここまでお読みいただいた方は、きっとこう感じているかもしれません。
「なるほど。うちでも何か提案できるかもしれない」
「でも、制度ってやっぱり難しそう…」
「他の会社がどうやってるのかも知りたいな」
それが、自然な気持ちです。そしてそれこそが、次の一歩を踏み出す準備が整った証拠だと私は思います。
🔁 本記事のまとめ
- 技術提案評価SI型は、現場からの技術提案を正式に評価する新しい発注方式。
- 脱炭素・省人化・安全性・維持管理性などが評価対象になり、価格だけではなく「価値」で勝負できる。
- 中小企業の現場の工夫や独自技術も提案可能。むしろ大手より柔軟に対応できる可能性がある。
- 成功のカギは、「提案内容の言語化」「制度を熟知した支援パートナー」「タイミングの見極め」。
🌱 「やってみよう」が未来を変える
制度や申請の話になると、「うちは関係ない」「そんな時間も余裕もない」と感じてしまうのも無理はありません。でも実は、ほんの小さな一歩――“相談してみる”だけでも、大きな差が生まれます。
あなたの会社が、これまで現場で培ってきた知恵や工夫は、決して「当たり前」なんかじゃありません。それは、未来の公共工事に求められる“価値そのもの”です。
👣 最初の一歩を、私たちが伴走します
市川市を拠点に、建設業者さまの許認可申請・制度対応・資金調達支援を行っている当事務所では、「制度の活用」に関するご相談を受け付けています。
- 「SI型って自社でも関われるの?」
- 「提案書ってどう作ればいいの?」
- 「まずはどんな補助制度があるの?」
こんな“ふわっとした相談”からで大丈夫です。
現場出身・行政経験者の視点で、実務に寄り添ったご提案をいたします。
あなたの現場の知恵が、地域を変える力になる。
その第一歩を、制度の理解から始めてみませんか?
小さな一歩が、未来の選ばれる力になります。