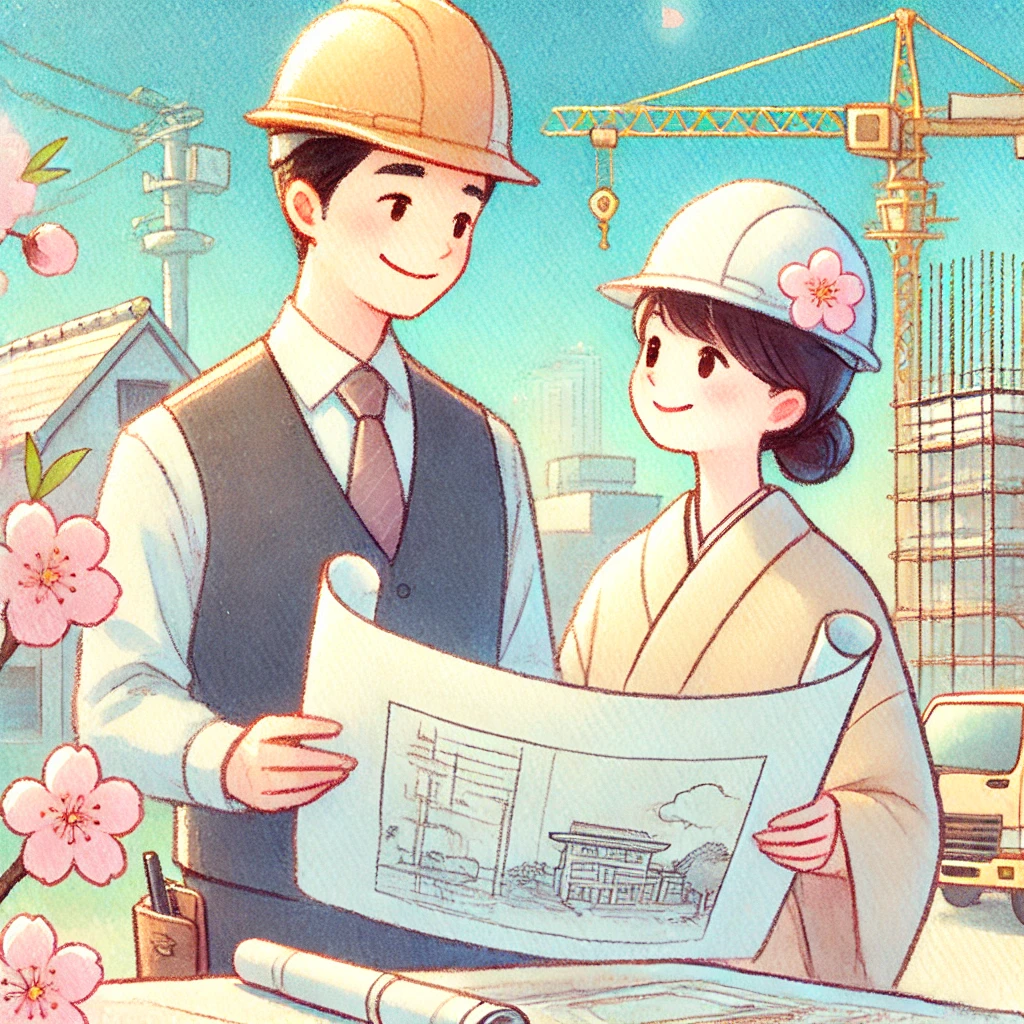目次
建設業の未来を守る手続き、誰が支えてくれるのか?
「社長、また制度が変わるらしいですよ」
「今度は下請法も厳しくなるって……ウチ、影響あるんですかね?」
市川市内のある現場監督さんが、そうぼやいたのはつい先日のことでした。建設業を営む皆さんの多くが、現場の忙しさに追われる一方で、制度改正や法令対応にまで目を配る余裕はなかなかありません。
2025年4月、政府は「下請法・下請振興法」の改正案を衆院で可決しました。これにより、建設業界でも価格交渉や支払い方法について厳しいルールが求められる時代へとシフトしています。「建設業法とは別枠だからウチは関係ない」と思っていたら、実はそうでもなかった——そんなケースも増えそうです。
私たち行政書士ができることは、「ただの申請屋」で終わることではありません。建設業者の皆さんが、制度変更の波にのまれず、むしろ“活かす側”になれるよう、手続きの整備と経営支援をお手伝いするのが私たちの使命です。
特に、市川市のように地場産業が地域経済を支えているエリアでは、建設業者の一手一手が地域の未来を左右します。だからこそ、現場に寄り添い、行政の思考と現実のギャップを埋める存在が必要です。
次章では、実際に市川市や周辺地域でどんな“現場のリアル”があるのかをご紹介します。そして、制度がどう変わり、どんな対応が必要になるのか——行政書士の視点から、わかりやすく解説していきます。
その書類、誰が整備する?
〜市川の現場が抱える“見えないリスク”とは〜
「うちは昔からのやり方でやってるから、大丈夫だよ」
——そう話していた市川市内の解体工事業者の社長が、最近になって慌てて相談に来られました。
きっかけは、公共工事の元請け業者からの“価格協議”の打診。
「説明資料がないと話にならない」「代金設定が不透明だと、今後の発注は見直す」と言われ、焦って顧問税理士に相談したものの、建設業法や下請法の話まではカバーしきれず、当事務所へ辿りついたのです。
このように、中小建設業者が直面しているのは「実際の取引内容をどう正当化するか」「書面でどう残すか」という“法制度とのギャップ”です。
特に市川市のような地域密着型の建設会社は、地元の信頼と経験で仕事を回してきた背景があり、どうしても書類対応や制度整備が後回しになりがちです。
さらに、ここ最近では以下のような課題も浮き彫りになっています。
- 💸 未だに手形払いが残っている現場
→ 改正下請法では“手形NG”、電子記録債権やファクタリングも「満額現金化」が難しい場合は認められない方向に。 - 📄 価格交渉の記録がない
→ 一方的な代金決定は“指導対象”。「うちは話し合ってるつもり」では通用しない。 - 🧾 BCP(事業継続計画)の未整備
→ 災害時に「社員と現場を守れる体制」が求められつつあり、補助金申請でも重要視される要素に。
実は、こうしたリスクを抱えたまま業務を続けている事業者は少なくありません。ハローワークの求人票を見ても、「特定技能あり」「外国人可」と記載されているのに、契約書や受入体制が整備されていない——そんな“ズレ”が多く見られます。
書類を整えることは、ただの形式ではなく“企業の防御力”を高める武器になります。そして、それをどこまで備えられているかで、今後の受注の質も変わってくるのです。
次章では、こうした課題に対して、行政書士としてどう寄り添い、どんな支援ができるのかを、最新の法改正も交えて分かりやすくお伝えします。
建設業者にも関係する“下請法”と“建設業法”の接点とは?
〜行政書士が解説する「知らなかった」では済まされない制度の話〜
「うちは建設業だから“下請法”は関係ないでしょ?」
そう思っていませんか?実は、今その“思い込み”が危険信号なのです。
2025年4月、政府が提出した下請法・下請振興法の改正案が衆院を通過し、2026年1月1日から施行される見込みとなりました。この改正案、建設業にとっても他人事ではありません。
✅ 建設業法と下請法——実は“線引き”が曖昧に
従来、建設工事の下請取引には「建設業法」が適用されるため、「下請法の対象外」とされてきました。しかし今回の国会審議では、建設業法と下請法を“有機的に連携”させる方向性が明言されています。
「建設業法でカバーしきれない不公正取引があれば、今後は“下請法”や“独占禁止法”による措置請求を活用する」と政府は答弁しています。
つまり、形式上は建設工事でも、実質的に下請的性質があれば“下請法の対象になる可能性がある”ということ。除雪作業や資材製造、設計図作成などがその例として挙げられました 。
🔍 改正下請法の主なポイント
- ⛔ 価格交渉をせずに一方的に代金決定する行為の禁止
- 💬 協議を拒否したり、必要情報を出さない企業は指導対象に
- 📝 支払いに手形を使うことは禁止
- 💳 電子記録債権・ファクタリングも“現金化できないならNG”
特に中小の建設業者にとって、こうした「商習慣の見直し」は負担でもありますが、補助金や入札での評価にもつながるため、早めの対応が大切です。
💡 なぜ行政書士の支援が必要なのか?
行政書士は、「建設業許可」だけでなく、以下のような形で多面的に支援できます。
- ✅ 契約書の整備(価格交渉の記録保持を含む)
- ✅ 制度変更に合わせた支払い条件の見直し
- ✅ BCPや就業規則と連動した企業体制の強化
- ✅ 公的補助金申請での“コンプライアンス加点”支援
さらに、松野行政書士事務所では、元自衛官として危機管理・災害対応にも通じているため、制度対応だけでなく現場目線でのリスク管理にも対応可能です。
次章では、こうした制度対応を実際にどう“行動に落とし込むか”、すぐに取り組める方法をご紹介していきます。
建設業者が“明日から”始められる制度対応3ステップ
〜手続きが経営を守る武器になる〜
「制度の話は分かった。でも、ウチにできることなんてあるのか?」
そんな疑問を持たれる方も多いと思います。実際、現場は忙しく、人も足りず、日々の業務だけで精一杯——それが中小建設業のリアルです。
でも、ご安心ください。すべてを一気に変える必要はありません。
行政書士として現場の声を聞いてきた立場から、“明日からできる制度対応”を3ステップでご紹介します。
🔹ステップ①契約書と見積書を「証拠資料」に変える
まず、価格交渉の証拠を残すための契約書や見積書を整備しましょう。
改正下請法では「交渉せずに一方的に金額を決めた」場合、指導対象となります。
今までは「口頭で決めた」「FAXで済ませた」というやり方も、今後はトラブルの火種に。
📌 実務ポイント
- 金額の根拠となる見積書を2通作成(発注側・受注側それぞれが保管)
- 契約書には「価格協議の結果」を明記
- 単価変更がある場合は、変更契約を文書で残す
🧾 当事務所では、実際の現場に合わせた雛形作成や、既存契約書の見直しも行っています。
🔹ステップ②支払い方法を「現金化可能な手段」に切り替える
手形払いが禁止される今、支払い手段の見直しも急務です。
電子記録債権やファクタリングも、「支払い期日までに満額で現金化できない場合」はアウト。
📌 実務ポイント
- 支払い方法は「銀行振込(現金決済)」が基本
- 下請に支払うサイクルを社内で明文化(例:締日と支払日を明記)
- 下請からの「期日明記」の要望には真摯に対応する
🔹ステップ③「BCP(事業継続計画)」を“最低限”だけでも用意する
災害時や緊急事態に備えたBCP(事業継続計画)は、補助金申請の加点要素にもなります。
「ウチには無理」と思いがちですが、最初はA4・1枚の簡易版からでもOKです。
📌 最低限押さえる内容
- 社員の安否確認体制(連絡網の整備)
- 主要資材・重機の調達経路と代替手段
- 担当業務のバックアップ体制(代理対応の仕組み)
🛡 当事務所では、元自衛官としての災害対応経験を活かし、建設業向けのBCPテンプレートを提供中。面談時にはヒアリングをもとに作成支援も可能です。
🔧 このように、「制度対応=負担」ではなく、「制度対応=経営を守る武器」として考えることが大切です。
市川市やその周辺では、制度整備が後回しになっている事業者も多く、そこに対応できるだけで競合と差がつきます。
次章では、そうした変化に一歩踏み出すための“きっかけ”を作るまとめと行動提案をお届けします。
制度に強い会社が、次の時代を生き抜く】
〜現場の未来を守るのは、社長の「一歩の行動」から〜
いま、建設業を取り巻く環境は静かに、しかし確実に変化しています。
価格交渉や支払い方法といった「これまでの当たり前」が通用しなくなる時代。制度は複雑で、現場は忙しい。でも、その波にどう立ち向かうかで、企業の未来が決まるのです。
今回お伝えしたように、下請法と建設業法の連携強化によって、建設業者も「交渉力」「説明力」「記録力」が問われる時代になりました。
それは言い換えれば、「ちゃんとやっている会社が評価される」時代です。
そして、その“ちゃんとやる”をサポートできるのが私たち行政書士です。
市川市という地域に根ざし、建設業者の実情を理解しているからこそ、現場に即した提案ができます。元自衛官として災害現場を見てきたからこそ、「制度と現実のズレ」を埋める支援ができます。
📩 次の一歩に迷ったら、まずはご相談ください
「うちも準備を始めないと…でも何から手を付ければいいか分からない」
そんな時は、まず30分のZoom相談からご利用ください。
- 書類の整備はどう始めるべきか?
- 支払い方法や契約書の見直しは?
- 補助金やBCPで加点を取るには?
実際にご相談いただいた多くの経営者が、「もっと早く相談すればよかった」とおっしゃいます。
あなたの事業を守るのは、今日の“気づき”を“行動”に変えることです。
🧱「制度対応 × 経営支援」で建設業の未来を一緒に築く
行政手続は単なる“書類”ではなく、経営を守る“仕組み”です。
松野行政書士事務所では、建設業に特化した経験と専門性を活かし、地域とともに歩むパートナーであり続けます。
一緒に、制度の波を“追い風”に変えていきましょう。
あなたの“現場力”が、これからの市川を支える力になります。