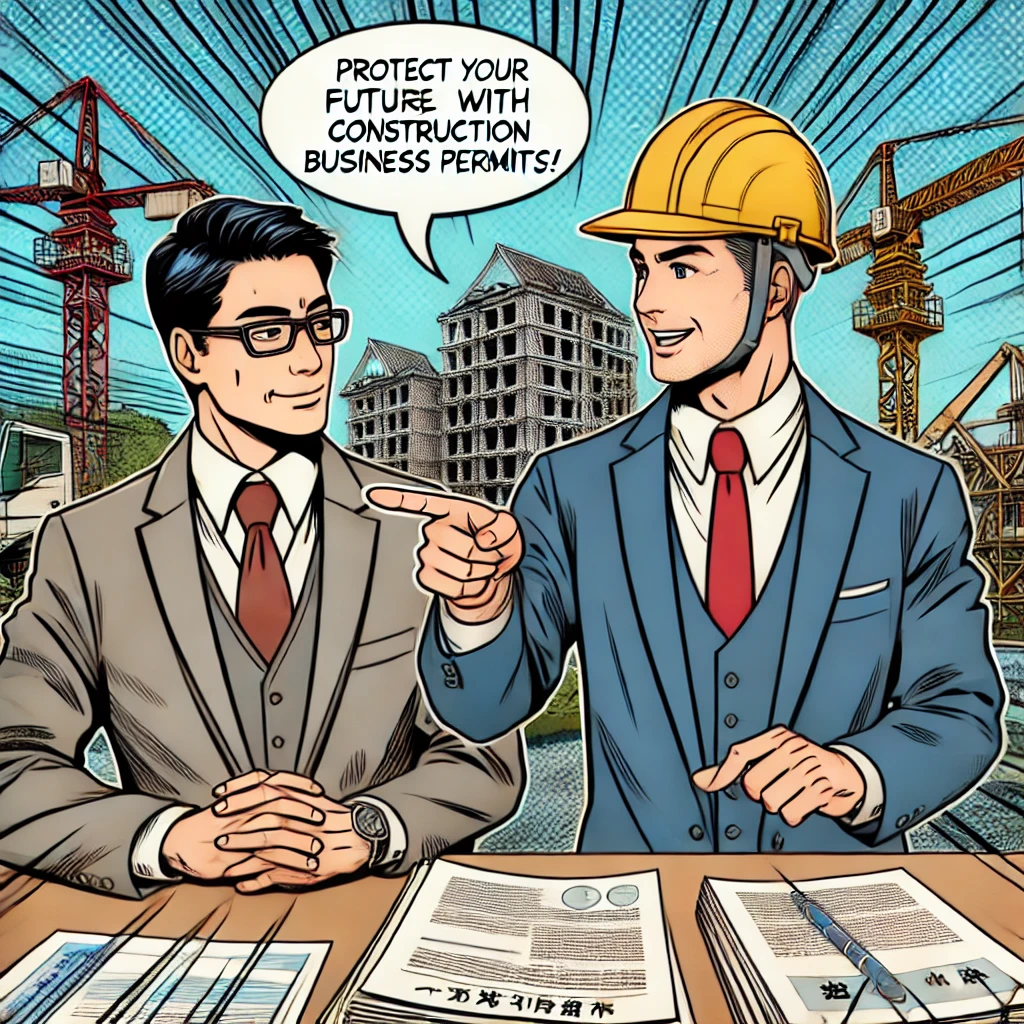千葉県市川市で建設業を営む皆さん、こんなことで悩んだことはありませんか?
「うちは軽微な工事しかしてないけど、建設業許可って必要?」
「そもそも許可が取れるのか、誰に相談すればいいか分からない」
現場は日々忙しく、社長も現場監督も事務も一人何役もこなしているのが現実。そんな中で「許可のことを調べる時間がない」「相談したいけど、誰が親身になってくれるのか不安」と感じている方は少なくないはずです。
特に市川市のように中小規模の建設業者が多い地域では、制度の複雑さに悩まされている方が多くいらっしゃいます。
でも、安心してください。
私たち行政書士は、まさにそうした“現場の声”に寄り添うために存在しています。そして、ここ市川市で開業した私・松野芳賢は、「建設業界を元気にしたい」という思いを胸に、日々、建設業許可や融資サポートに奔走しています。
この記事では、建設業許可の背景や制度の動き、市川市の現場で起きているリアルな課題、そして行政書士がどのようにお役に立てるのかをわかりやすくお伝えしていきます。
目次
「親方、うちって許可取ってないんですか?」──市川の現場でよく聞く“ちょっと怖い話”
建設現場では、職人たちの会話から思わぬ問題が浮かび上がることがあります。
ある日、市川市内で解体工事を請け負っていた個人事業の親方が、こんな相談をしてくれました。
「うちの若いのが、元請さんに“建設業許可はあるんですか?”って聞かれたって焦っててさ……正直、自分でもよく分かってないんだよね」
実はこのケース、決して珍しくありません。
特に「500万円未満の軽微な工事しかやっていないから、うちは許可は不要」と思い込んでいる事業者さんは多いのですが、実際にはグレーゾーンの仕事をしているケースも散見されます。
「うちは元請じゃないから大丈夫」──本当に?
最近では、公共工事だけでなく民間の元請業者でも、下請け業者に対して建設業許可の有無を厳しく確認する流れが強まっています。
品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)の改正や、元請責任の強化などが背景にあり、「許可がない=リスク」と見なされる時代になってきているのです。
市川市内のある外構業者の話
市川市で10年以上外構工事をしてきたA社も、ある日突然、元請からこう言われたそうです。
「次の案件からは、建設業許可がないと契約できません」
慌てて手続きを調べたものの、情報が複雑で何から手をつけていいか分からず、弊所にご相談いただきました。
結果的に、その方は「とりあえず相談だけ」のつもりが、要件を満たしていることが分かり、スムーズに申請手続きへ。
2ヶ月後には無事に許可証が交付され、元請との関係も継続できたとのことでした。
「建設業許可って結局どういう制度?」──行政書士がやさしく解説します
建設業の仕事をしていると、「建設業許可」という言葉を聞かない日はないかもしれません。
でも、いざ説明しようとすると「29業種?500万円の壁?経管って何?」といった疑問が次々に浮かんでくるはずです。
ここでは、現場の方でもわかるように、許可制度のポイントを整理してみます。
建設業許可が必要になるのは、こんなとき
許可が必要になる基準は、ズバリ以下の金額です。
- 工事1件の請負金額が500万円(税込)以上(建築一式工事は1,500万円)
- もしくは延床面積が150㎡を超える木造住宅の工事
つまり、「今まで軽微な工事ばかりだったけど、ちょっと大きな案件を受けるかも…」というタイミングで、許可が求められるケースが出てくるんです。
許可取得の「5つのハードル」
許可を取るには、以下のような要件を満たす必要があります:
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
→ 過去5年(法人なら役員、個人なら本人)に一定の経営経験が必要です。 - 専任技術者がいること
→ 施工管理技士や10年以上の実務経験がカギ。 - 誠実性があること
→ 過去に法令違反があるとNGになる場合も。 - 財産的基礎があること
→ 自己資本500万円以上 or 直近決算で純資産が500万円以上。 - 欠格要件に該当しないこと
→ 暴力団関係者や破産手続き中の方は対象外です。
よくある誤解を整理します
❌「うちは個人事業主だから許可はいらない」
✅ 許可の要否は法人・個人を問わず、金額と工事内容で決まります。
❌「親方が10年やってきたから資格はいらない」
✅ 経験10年を証明するためには、契約書や請求書など証拠資料が必要です。
❌「前に許可持ってたからすぐに再取得できる」
✅ 一度失効すると、書類や証明の再提出が必要になります。
制度が難しく感じるのは当然です。
でも、行政書士は「制度と現場の橋渡し役」として、こうした書類の整備や要件の見極めをお手伝いすることができます。
「許可が必要かも」と思ったら…建設業者が“今すぐできる”3つの行動
制度の話を聞いて、「うちもそろそろ許可を取らなきゃマズいかも…」と感じた方へ。
建設業許可の取得は、ただの書類仕事ではありません。会社の信用力を高め、仕事の幅を広げる重要なステップです。
とはいえ、何から始めたらいいのか分からない方のために、今日からできる3つの行動をお伝えします。
① 「経営経験」や「工事の実績」を整理する
まずは、自社または代表者個人としての経営経験・工事実績を簡単に書き出してみましょう。
- 法人の設立年月日、または個人事業としての開業時期
- 過去に請け負った工事の契約書・請求書・写真など
- 工事金額と工種(例:外構工事、内装仕上げ、塗装など)
📌 Point:証拠書類がないと経験年数がカウントされません。
→ 契約書や見積書、通帳の振込履歴なども有効です!
② 資金要件の「見える化」をする
建設業許可には、最低でも500万円以上の資金力が求められます。
こんな書類が使えます
- 銀行の残高証明書(直近1ヶ月以内)
- 貸借対照表(直近の決算書)で自己資本が500万円以上
💡 経営者の個人口座でもOKな場合があります(個人事業主や設立間もない法人の場合)。
建設業の未来を守るために、今こそ「一歩」を踏み出そう
建設業許可は、単なるお役所手続きではありません。
それは、会社の信用力を証明し、より良い仕事につながる「信頼のパスポート」のようなものです。
とくにここ市川市では、公共工事や元請案件での許可要件が厳しくなりつつあり、今後さらに「許可の有無」が選ばれる条件となっていくでしょう。
一人で悩むより、「一緒に考える」専門家がいます
- 「許可を取れるか不安」
- 「書類を集める時間がない」
- 「どの業種で出せばいいのか分からない」
そんな悩みは、行政書士にご相談いただければ、一つずつ丁寧に整理し、道筋をご案内できます。
私たち松野行政書士事務所では、市川市で開業以来、建設業界に特化してサポートしてきました。
「実質無料の有料相談(※契約時に相談料相殺)」など、相談しやすい体制も整えています。
建設業を続けていくには、「信用」と「法令順守」がますます大切になってきます。
今できる一歩が、未来の仕事と信頼をつなぐ橋になります。
どうか、その一歩を、私たちと一緒に踏み出してみてください。