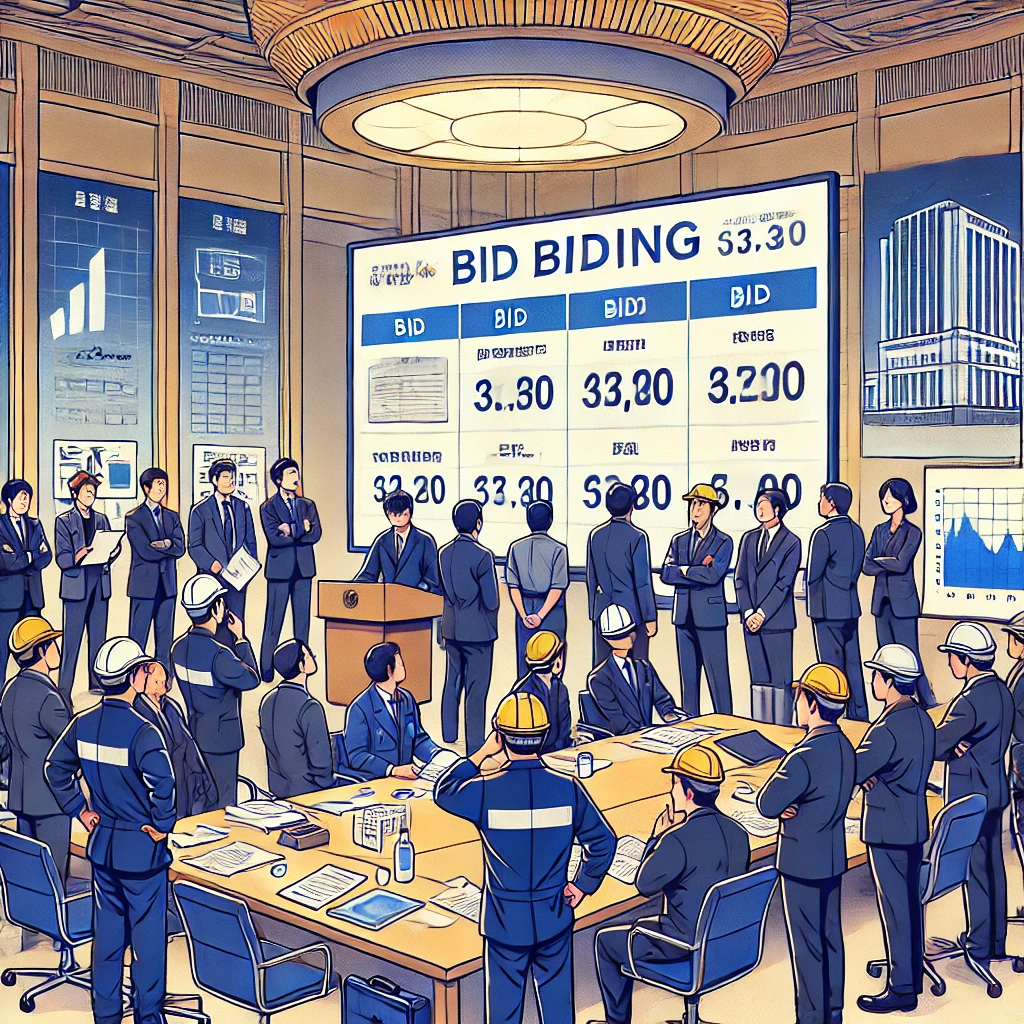目次
関西圏の落札率が全国で最も低い理由とは?
「最近、公共工事の競争が激しくなってきた…」
「最低制限価格を意識しないと、なかなか落札できない」
建設業界に携わる皆さんなら、入札に関するこうした悩みを感じたことがあるのではないでしょうか?
最新の調査によると、市区町村の平均落札率が最も低かったのは滋賀県の88.2%(2023年度実績、政令市を除く)で、90%を下回っていたのは 滋賀県、兵庫県、大阪府、京都府、奈良県と、いずれも関西圏 という結果になりました。
つまり、関西圏の建設業者にとっては、「厳しい価格競争にさらされている」 という現状があるわけです。
また、奈良県のように 最低制限価格を事前公表している自治体では落札率が低い傾向 にあることも分かりました。
では、なぜ関西圏では落札率が低いのでしょうか?
また、今後の入札で生き残るためにはどのような対策が必要なのでしょうか?
✅ この記事で分かること
- 関西圏の落札率が低い理由とは?
- 最低制限価格の公表が与える影響
- 建設業者が取るべき対策と活用できる制度
入札に関する知識は、経営の安定につながる重要なポイントです。
次の章では、落札率の低さが生じる原因を、現場のリアルな視点から深掘りしていきます。
なぜ関西圏の落札率は低いのか?
「最近、落札価格がどんどん下がっている…」
「ギリギリの価格で受注しても、利益が出ない」
関西圏の建設業者からは、落札率の低下 に関する声が多く聞かれます。
では、なぜ関西圏では落札率が低くなっているのでしょうか?
📌 落札率が低い原因①:最低制限価格の事前公表
奈良県など一部の自治体では、最低制限価格を事前公表 しています。
これにより、入札者が最低制限価格ギリギリで応札しやすくなり、価格競争が激化 しているのです。
実際に、最低制限価格を事前公表している市区町村の平均落札率は91.7% ですが、
事後公表(落札後に公表)している市区町村では93.7% となっており、2ポイントの差 が生じています。
📌 落札率が低い原因②:ダンピング対策が不十分
品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)では、過度な低価格受注を防ぐため、適正な最低制限価格の設定を求めています。
しかし、関西圏の一部自治体では、
✅ 最低制限価格の計算方法が古い(2019年以前のモデルを採用)
✅ 中央公契連モデル(公契約の全国基準)の最新算定式を使っていない
など、十分なダンピング対策が取られていないケースもあります。
その結果、過度な価格競争が発生し、落札率が全国平均より低くなる 傾向があるのです。
📌 落札率が低い原因③:関西圏の競争環境
関西圏は、大手ゼネコンから中小企業まで幅広い業者がひしめく市場 です。
特に都市部では、多くの業者が同じ案件に入札するため、価格競争が激化しやすい 状況にあります。
例えば…
✅ 大阪府では、同じ規模の工事でも関東より多くの業者が入札に参加する
✅ 関西圏では、積極的に低価格戦略を取る業者が多い
こうした市場特性も、落札率が低くなる要因の一つ と考えられます。
⚠ 現場の影響:「価格競争の激化」がもたらすリスク
落札率が低くなることは、一見すると発注者にとってメリットが大きいように思えますが、建設業界全体には以下のようなリスクをもたらします。
❌ 過度な低価格受注による手抜き工事のリスク
❌ 下請け企業への過度なコスト削減要請(しわ寄せ)
❌ 労働環境の悪化(適正な賃金が払われない・安全管理の甘さ)
品確法の運用指針でも、こうしたリスクを防ぐために
✅ 低入札価格調査基準の見直し
✅ 最低制限価格の適正な設定
が求められています。
📢 では、関西圏の建設業者はどう対応すべきか?
✅ 落札率の動向を分析し、適正価格での応札を意識する
✅ 最低制限価格の公表状況をチェックし、競争環境を把握する
✅ 価格競争だけでなく、技術力・提案力で差別化を図る
次の章では、行政書士の視点から、入札における重要なポイントや実務的な対策について詳しく解説します。
落札率を左右する「最低制限価格」の仕組みとは?
「なぜ最低制限価格が公表されると、落札率が下がるのか?」
「ダンピング対策をしている自治体とそうでない自治体の違いは?」
建設業の入札において、最低制限価格は落札率を大きく左右する重要な要素です。
ここでは、行政書士の視点から 「最低制限価格の仕組み」 を分かりやすく解説します。
🔍 最低制限価格とは?
最低制限価格とは、異常に低い価格での落札を防ぐために設定される最低限の入札価格 のことです。
最低制限価格を下回ると入札失格 となるため、建設業者にとっては「どの価格で入札するか」を決める際の重要な基準になります。
✅ 最低制限価格の目的
- 過度な価格競争を防ぐ(ダンピング防止)
- 適正な施工品質を確保する
- 労働環境や安全管理の維持
📌 最低制限価格の公表方法で変わる落札率
今回の調査では、最低制限価格の公表方法が落札率に影響を与えている ことが分かりました。
| 最低制限価格の公表方法 | 市区町村の平均落札率 |
|---|---|
| 事前公表(入札前に公開) | 91.7% |
| 事後公表(落札後に公開) | 93.7% |
💡 事前公表すると落札率が低くなる理由は?
- 最低制限価格が分かるため、入札者がギリギリの価格を狙いやすい
- 価格競争が過熱し、結果的に落札率が下がる
- 落札価格の低下 → 利益率の低下 → 施工品質への悪影響 という悪循環に
📌 最低制限価格の設定方法による影響
最低制限価格は、各自治体が 独自の算定式 を用いて決定しています。
特に、中央公契連モデル(全国統一の基準)を採用しているかどうか が重要なポイントです。
| 最低制限価格の設定基準 | 市区町村の平均落札率 |
|---|---|
| 2019年モデル以前を採用 | 92.5% |
| 最新の2022年モデルを採用 | 93.9% |
💡 古い算定式を使っていると落札率が低くなる理由は?
- 最低制限価格が低めに設定されるため、全体の落札価格も下がる
- 適正価格を確保できず、ダンピング(過度な低価格競争)が起こりやすい
- 新しい基準を採用した自治体ほど、落札率が高く安定している
⚠️ 最低制限価格が適正でないと起こるリスク
最低制限価格の設定が適切でない場合、次のようなリスクが発生します。
❌ 過度な価格競争による施工品質の低下(安全基準が守れない)
❌ 下請け企業への負担増加(資材・人件費を削らざるを得ない)
❌ 事業者の利益圧迫による倒産リスクの増加
このため、品確法では
✅ 低入札価格調査基準の見直し
✅ 最低制限価格の適正な設定
を自治体に求めています。
📢 では、建設業者はどう対応すべきか?
最低制限価格の公表状況や算定基準を把握することが重要!
✅ 入札案件ごとに最低制限価格の公表方法をチェックする
✅ 自治体の最新の算定基準(2022年モデル採用など)を確認する
✅ 価格だけでなく、施工実績や技術提案で差別化を図る
次の章では、建設業者が入札に強くなるための具体的な対策 や 活用できる制度 について詳しく解説します。
建設業者が入札で勝つための具体的な対策と活用できる制度
最低制限価格の設定や公表方法が落札率に大きな影響を与えることが分かりました。
しかし、建設業者にとって大切なのは、「どうすれば競争に勝ち、適正な価格で受注できるのか?」ということです。
ここでは、 「価格競争だけに依存せず、入札を有利に進めるための戦略」 を3つ紹介します。
✅ 1. 価格以外の「加点要素」を強化する
落札価格が低くなりやすい環境では、価格以外の要素で他社と差をつける ことが重要になります。
近年、多くの自治体が「総合評価方式」を採用しており、価格だけでなく 技術力や施工実績 も評価されるケースが増えています。
💡 加点要素を強化するための具体策
🔹 経営事項審査(経審)の評点を向上させる(技術力・経営力を評価)
🔹 施工実績や技術提案書の充実(自治体が求める品質基準をアピール)
🔹 ISO認証やBCP(事業継続計画)などの取得(信頼性を高める)
📌 行政書士ができるサポート
✅ 経営事項審査(経審)の評点アップに向けたアドバイス
✅ 技術提案書や申請書類の作成支援
✅ ISO認証やBCP策定のサポート
✅ 2. 自治体ごとの最低制限価格の動向をチェック
同じような案件でも、自治体によって最低制限価格の設定基準が異なる ため、事前に情報を収集することが大切です。
💡 最低制限価格の動向を調べる方法
🔹 入札公告や落札結果を定期的にチェック(自治体のWebサイトを活用)
🔹 「中央公契連モデル」の最新動向を確認(基準の変更に対応)
🔹 過去の落札データを分析し、適正な入札価格を見極める
📌 行政書士ができるサポート
✅ 自治体ごとの最低制限価格の調査
✅ 過去の落札データを活用した戦略立案
✅ 競争環境を踏まえた入札価格のアドバイス
✅ 3. 補助金や助成金を活用し、資金力を強化する
価格競争が激化する中で、安定的に受注を続けるためには 経営基盤を強化 することも欠かせません。
自治体や国の補助金・助成金を活用することで、設備投資や技術力向上を図ることが可能です。
💡 活用できる補助金・助成金の例
🔹 事業再構築補助金(新規事業への参入を支援)
🔹 ものづくり補助金(設備投資や技術開発を支援)
🔹 建設業向けのDX補助金(デジタル技術導入を支援)
※厚生労働省が管轄する 助成金の申請手続きは、法律により 社会保険労務士の独占業務と定められています。そのため、当事務所では対応できませんが、 提携している社会保険労務士事務所をご紹介 することは可能です。
📌 行政書士ができるサポート
✅ 建設業向け補助金の申請サポート
✅ 設備投資や事業拡大に関する資金調達のアドバイス
✅ DX(デジタル化)推進の支援
📢 価格だけに頼らず「総合力」で勝つ!
関西圏では価格競争が激化し、落札率が低い状況が続いています。
しかし、「最低制限価格の動向を把握する」「加点要素を強化する」「補助金を活用する」などの対策を講じることで、価格だけに頼らず受注機会を増やすことができます。
次の章では、「今すぐできる具体的なアクション」 をまとめます!
関西圏の落札率低下にどう対応すべきか?
関西圏では、最低制限価格の公表方法やダンピング対策の不十分さが影響し、全国的に見ても落札率が低い傾向にあります。
過度な価格競争に巻き込まれないためには、価格以外の要素で強みを作ることが重要 です。
では、建設業者が 今すぐできる3つのアクション をまとめます。
✅ 1. 最低制限価格の公表状況を把握し、戦略的に入札する
📌 具体的な行動
🔹 入札公告や落札結果を定期的に確認(自治体ごとの価格動向を把握)
🔹 最低制限価格の公表方法(事前公表 or 事後公表)をチェック
🔹 中央公契連モデルの最新動向を調べ、落札率の変化を分析
🔍 こんな方にオススメ!
✅ 「落札率の低下で、入札に苦戦している…」
✅ 「適正な価格設定が分からない…」
📢 行政書士がサポートできること
✅ 自治体ごとの最低制限価格の調査
✅ 過去の落札データをもとにした入札戦略の策定
✅ 2. 価格以外の加点要素を強化し、競争力を高める
📌 具体的な行動
🔹 経営事項審査(経審)の評点アップを図る(技術力・財務力をアピール)
🔹 施工実績・技術提案の充実(総合評価方式に対応)
🔹 ISO認証・BCP(事業継続計画)の取得を検討
🔍 こんな方にオススメ!
✅ 「技術力はあるのに、価格競争で負けてしまう…」
✅ 「総合評価方式での評価を上げたい!」
📢 行政書士がサポートできること
✅ 経営事項審査(経審)の評点向上のアドバイス
✅ 技術提案書の作成支援
✅ 3. 補助金・助成金を活用し、経営基盤を強化する
📌 具体的な行動
🔹 事業再構築補助金やものづくり補助金の活用を検討
🔹 建設業向けDX(デジタル化)補助金を活用し、業務効率を向上
🔹 設備投資や事業拡大のための資金調達を計画的に行う
🔍 こんな方にオススメ!
✅ 「価格競争の負担を減らし、安定した経営を目指したい!」
✅ 「補助金を活用して、最新技術を導入したい!」
📢 行政書士がサポートできること
✅ 建設業向け補助金の申請サポート
✅ 資金調達のアドバイス
🏗️ 行政書士が、建設業の入札戦略をサポート!
関西圏の落札率低下は、単なる価格競争の激化だけでなく、最低制限価格の設定方法や公表の仕方も影響しています。
今後の入札戦略を考える上で、価格だけに依存しない「総合力」を高めることが重要 です。
📢 「入札で勝てる戦略を立てたい」「補助金を活用したい」「経審の評点を上げたい」
そんな方は、行政書士にご相談ください!