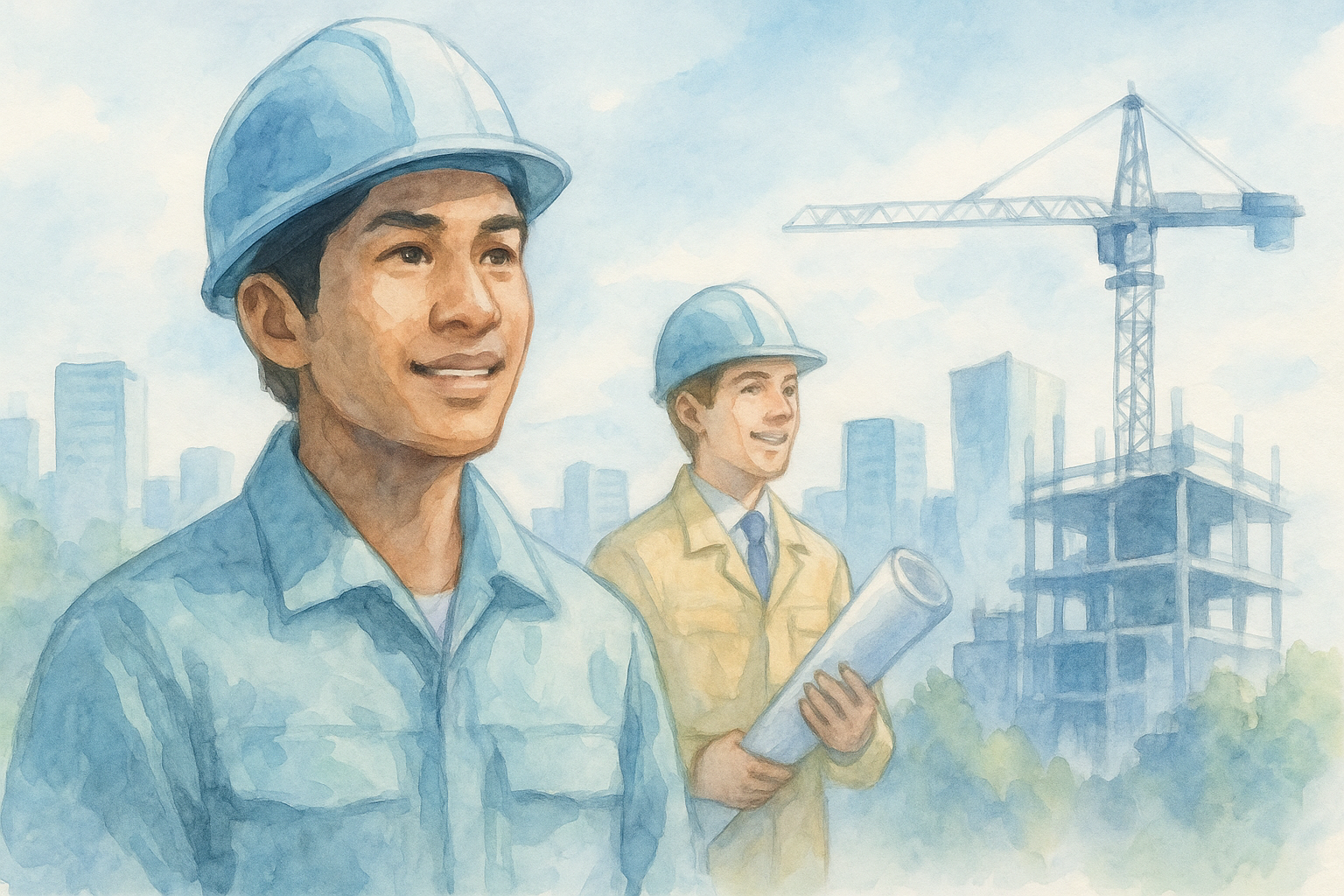目次
「インドネシアがトップ」に驚いた建設業の現場
外国人技能実習の勢力図が変わった
ここ数年、建設業界の現場では「外国人技能実習生=ベトナム人」というイメージが定着していました。
2017年度の制度開始以来、ベトナムは技能実習の新規認定件数で常にトップ。とくに2019年度には約4万7,000件とピークを記録し、全国の建設現場で多くのベトナム人技能実習生が活躍してきました。
ところが、2024年度のデータで状況が一変しました。
技能実習計画の新規認定件数でインドネシアが初めて最多(約3万2,000件)となり、全体の40%を占めています。長らくトップを維持してきたベトナム(約2万4,000件)を上回り、勢力図が大きく塗り替えられたのです。
この変化は、統計上の話にとどまりません。すでに全国の建設現場で「肌感覚として」変化を実感する声が増えています。
現場から聞こえる変化の声
「最近、募集してもベトナム人の応募が少なくなった」
「面接でインドネシア人が増えた」
「通訳がインドネシア語に変わっている」
こうした声は、大手ゼネコンから地場の中小工務店まで幅広く聞かれるようになっています。
とくに中小規模の建設会社では、外国人材が実際の施工体制を支える中核になっているため、この変化は経営にも直結します。
「人材のシフト」は経営課題になる
人手不足が続く建設業では、外国人技能実習生の存在は“補助的な戦力”ではなく“欠かせない戦力”になっています。これまで慣れ親しんできたベトナム中心の採用・受け入れ体制が変わることで、現場のオペレーションだけでなく、許可・制度対応、教育体制、資金計画にも影響が及びます。
この「インドネシアシフト」は、一時的なブームではなく、構造的な変化のはじまりです。
なぜこうした変化が起きたのか、そして企業として何を備えるべきなのか――ここを押さえることが、これからの建設業経営にとって重要な分岐点になります。
なぜインドネシア人材が急増しているのか
若年人口の多さと「送り出し政策」の積極性
インドネシアの技能実習生が急増している背景には、人口構成と政策の両面があります。
インドネシアでは国民の半数以上が15〜32歳という若年層で占められており、国内の労働市場だけでは十分な雇用機会を確保できていません。そのため政府としても、国外への人材送り出しを積極的に進める方針を取っています。
特に建設分野は、インドネシア国内での雇用機会が限られているため、日本への就労は「安定した収入が得られるチャンス」として高い人気を集めています。送り出し機関も制度面の整備を進めており、日本企業とのマッチングが活発化している状況です。
ベトナム側の事情も大きい
もう一つの大きな要因が、ベトナム人材の伸び悩みです。
かつて技能実習制度の主役だったベトナムでは、近年、経済成長とともに国内の雇用環境が改善。賃金水準も上がり、日本に来なくても安定した職を得られるケースが増えてきました。
2019年度に約4万7,000件あった新規認定件数も、2024年度には約2万4,000件とピーク時の半分ほどに減少。送り出し側の優先順位も、かつてほど日本一択ではなくなっています。
この流れが、インドネシアへのシフトを一層後押しする結果となっています。
現場で感じる「応募の質と量」の変化
現場の採用担当者からはこんな声も聞かれます。
「募集してもベトナムからの応募が集まりにくくなった」
「インドネシアからの応募は増えているが、通訳や文化対応に時間がかかる」
「送り出し機関の対応レベルに差がある」
インドネシア人材の増加はチャンスであると同時に、現場対応の質が問われる局面でもあります。
単に「数を確保すればいい」という時代ではなくなりつつあるのです。
採用競争が激しくなる可能性も
インドネシアの若年人口は豊富ですが、送り出し先は日本だけではありません。建設業だけを見ても、台湾や韓国、中東なども積極的に受け入れを拡大しています。
今後は、日本国内の建設会社同士でも採用競争が激しくなる可能性が高く、「早めの体制づくり」が重要になります。
制度と仕組みを押さえる ― 技能実習と特定技能の“いま”
技能実習計画は「採用の入口」
外国人材を受け入れるとき、多くの建設会社が最初に関わるのが技能実習制度です。
この制度では、企業が実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)の認定を受ける必要があります。
認定を受けることで初めて在留資格が発給され、受け入れが可能になります。
この「技能実習計画」は単なる書類ではなく、実習内容・受け入れ体制・待遇条件を明示する重要な計画書です。
特に建設分野では、安全管理や技能習得の工程が細かく求められるため、監理団体や送り出し機関との事前調整が不可欠です。
インドネシアが40%を占める新たな流れ
2024年度、建設分野の技能実習計画の新規認定件数は7万9,942件。
そのうちインドネシアが3万2,053件(40.1%)とトップを占めました。
長年首位だったベトナムは2万4,490件(30.6%)。勢いの差は明らかで、受け入れの主役が入れ替わったといえます。
フィリピン(8,140件)、ミャンマー(5,547件)、カンボジア(2,893件)といった国も増加傾向にあり、今後はさらに多国籍化が進む可能性もあります。
これは、企業側にも「柔軟な受け入れ対応」が求められることを意味します。
特定技能との連携で長期的な戦力に
技能実習は基本的に最長5年間で終了する仕組みですが、ここで重要になるのが特定技能への移行です。
建設分野では、技能実習を修了した人材が特定技能1号へスムーズに移行できる仕組みが整備されています。
つまり、単なる“短期労働力”ではなく、長期的な戦力として定着させる道が開けているのです。
この移行を前提に制度設計している企業と、そうでない企業では、数年後に大きな差が生まれます。
受け入れ体制を制度と合わせて考える
技能実習・特定技能ともに、制度上の要件と現場運用のバランスが欠かせません。
たとえば以下のような点は、実務上よく課題になります。
- 技能実習計画の作成・変更のタイミング
- 現場配置と職種区分の整合性
- 特定技能への移行時期の見極め
- 登録支援機関や監理団体との調整
制度を「あとから覚える」のではなく、採用段階から制度設計を組み込むことで、余計な手戻りやトラブルを防ぐことができます。
人材確保で後手に回らないための備え方
採用は「計画」ではなく「体制」づくりから
インドネシア人材が増える流れは、もはや一時的なトレンドではなく、建設業界全体の構造変化です。
この波に対応するには、採用そのものよりも前に「受け入れ体制を整える」ことが重要になります。
現場の実感として、「人が来ない」「すぐ辞める」「通訳がいない」という問題は、ほとんどが体制づくりの遅れに起因しています。
逆に、制度・言語・生活支援をあらかじめ整備している企業では、安定した人材確保と定着につながっているケースが多く見られます。
建設業許可・経営事項審査と人材の関係
外国人技能実習生や特定技能人材を受け入れるためには、建設業許可の業種や経営事項審査(経審)の状況も重要な要素です。
特に公共工事や元請けとしての工事を視野に入れる場合、
- 技能実習生を適切に配置できる業種許可があるか
- 雇用人数の変動によって経審の点数がどう変わるか
- 雇用管理体制の整備状況が入札評価に影響しないか
といった点を、採用と同時にチェックしておく必要があります。
人材戦略と許可・経審対策を切り離して考えると、後から制度対応で手間取る企業も少なくありません。
監理団体・登録支援機関の選定もカギ
技能実習や特定技能を円滑に進めるうえで欠かせないのが、監理団体・登録支援機関の選定です。
インドネシア人材の受け入れに慣れた団体かどうかで、現場の負担は大きく変わります。
- 通訳・生活支援のフォローが手厚いか
- 送り出し機関との連携体制があるか
- 現場とのコミュニケーションをどこまで担ってくれるか
こうした点を事前に確認することで、採用後のトラブルを最小限に抑えることができます。
処遇の「見える化」が採用力を高める
インドネシアの送り出し機関では、「日本での処遇情報」を求める傾向が強まっています。
賃金水準や勤務環境、安全対策をわかりやすく伝えられる企業は、優秀な人材から選ばれやすくなるのです。
単に「募集をかける」だけではなく、
- 仕事内容
- 住環境
- サポート体制
- 処遇水準
を整理し、説明できる形にしておくことが、これからの採用競争では大きな差になります。
「人材戦略=経営戦略」へ。備えが会社の未来を左右する
採用の話ではなく、経営の話
外国人材の増加は、単なる“人手不足の補填”ではなく、企業の経営方針そのものを問うテーマになっています。
技能実習や特定技能を受け入れるかどうかは、今や「必要か・不要か」ではなく、どう活かすかの段階に入っているといえるでしょう。
特にインドネシア人材の比率が高まっている今、受け入れに前向きな企業とそうでない企業では、数年後に現場力・売上・入札力で大きな差が出てくる可能性があります。
「人材戦略」はもはや経営戦略の一部。先に体制を整えた企業ほど、採用市場で有利になるのです。
先を見据えた資金計画・補助金の活用
人材受け入れの体制整備には、通訳支援・社宅・教育コストなど、ある程度の初期投資が必要です。
その際に有効なのが、補助金や助成金、金融機関による資金調達支援の活用です。
たとえば、
- 住宅環境整備に活用できる補助金
- 人材育成関連の助成金
- 事業計画と連動した融資枠の活用
といった制度をうまく組み合わせることで、中小企業でも無理のない形で受け入れ体制を強化することが可能です。
「専門家との伴走」で失敗リスクを減らす
技能実習や特定技能の制度は、表面上の手続きだけでなく、
- 許可要件
- 書類作成
- 経営事項審査との整合性
- 各種法令順守
といった複数の法的・制度的要素が絡み合っています。
このため、制度の全体像を把握していないまま進めると、受け入れ途中で申請漏れや運用上のトラブルが起こることも珍しくありません。
こうしたリスクを避けるために、行政書士など実務に詳しい専門家との伴走を活用する企業が増えています。現場のリアルな課題を踏まえながら、制度設計から資金計画までをワンストップで支援してもらえる体制は、結果的にコスト削減にもつながります。
いま、備える企業が勝つ
建設業の人材確保の構図は、確実に変わり始めています。
インドネシア人材の増加は、その変化の象徴といえる出来事です。
この波に「後追いで対応する」のか、「先回りして備える」のかで、企業の未来は大きく変わります。
- 受け入れ体制を整える
- 制度と経営を連動させる
- 外部リソースを上手に活用する
この3つを早い段階で進めておくことが、今後の採用競争・事業拡大で大きな武器になります。
「うちにはまだ早い」と思っているうちに、他社は静かに準備を始めています。
まずは、自社の許可状況・経審・人材計画を整理し、採用の土台となる“受け入れ体制”の現状把握から始めてみてください。