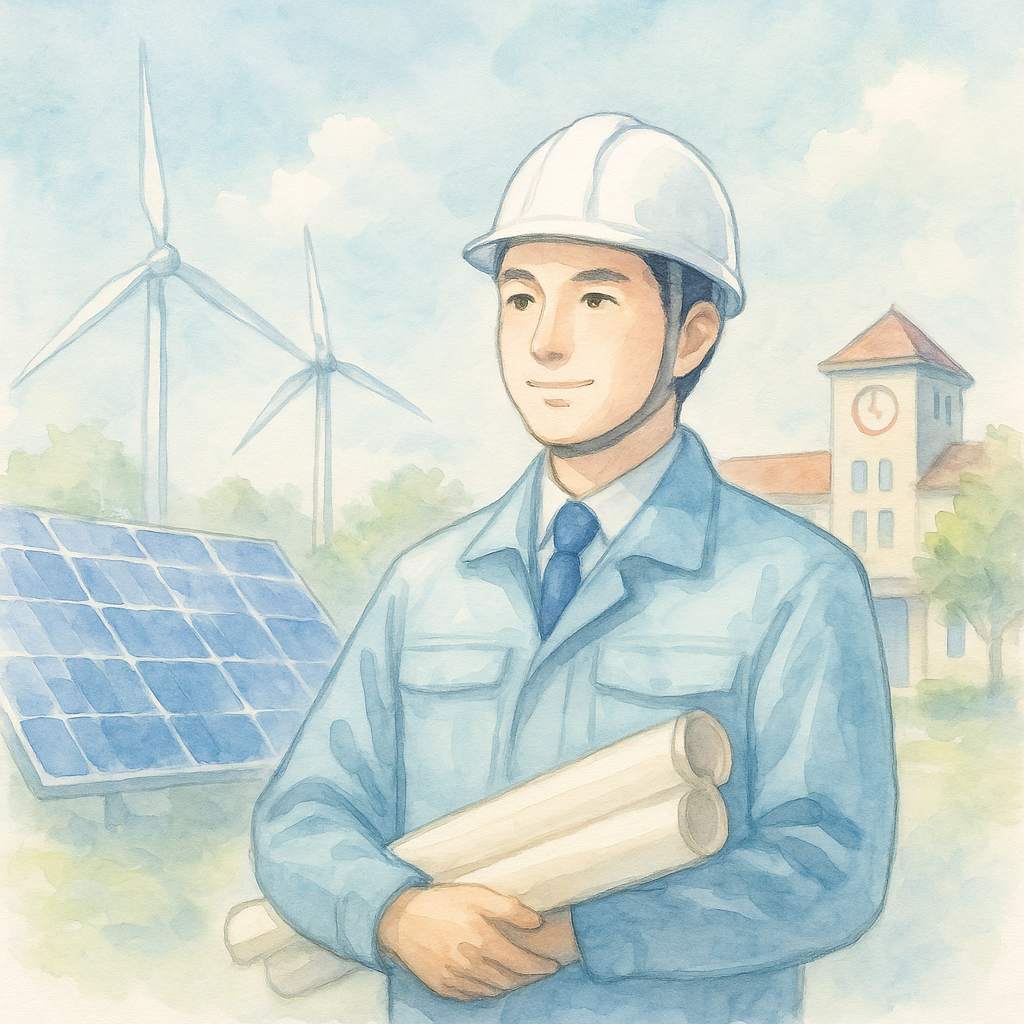目次
災害に強い街づくりと建設業の新しい役割
「もし大規模な停電が起きても、この施設なら電気が使える」
そんな安心感を地域に届けるために、環境省は2026年度予算案で防災拠点や避難所となる公共施設に再生可能エネルギーを導入するための補助金(50億円)を盛り込みました。
さらに、一戸建てや集合住宅の脱炭素化支援、太陽光パネルのリサイクル準備など、建設業と密接に関わる新しい制度が次々と検討されています。
こうした国の動きをニュースで見ても、「大手ゼネコンの話でしょ?」「うちのような中小には関係ない」と思う方も多いかもしれません。
ですが、実は補助金や経営事項審査(経審)、建設業許可をうまく組み合わせれば、中小建設会社にとっても資金調達や受注機会の拡大につながるチャンスになります。
この記事では、現場経営者・職人・後継者の方に向けて、
- なぜ今「補助金×建設業許可×経審」が重要なのか
- 制度をどう理解すれば現場の仕事に直結するのか
- 今日から取り組める具体的なアクション
をわかりやすく整理してお伝えします。
災害や資金繰りで悩む建設現場
「防災拠点の工事を受けたいけど…」の壁
ある中堅の建設会社の社長さんから、こんな声を聞きました。
「市役所の耐震補強や防災施設の改修工事に興味はあるけど、ウチはまだ公共工事の経験が少なくて…。経審も点数が低いし、入札にもなかなか参加できない」
実際、自治体が発注する公共工事は「建設業許可」と「経営事項審査(経審)」が必須。
許可を取っているだけでは不十分で、経審の点数がなければ門前払いになってしまいます。
「資金調達ができないから新規投資が難しい」
さらに、再エネ設備や省エネ工事の需要が広がっている一方で、
「設備投資や人員強化に回す資金が足りない」
「銀行融資は通りにくいし、補助金の情報も自分では追えない」
といった声も少なくありません。
補助金を知らずに自己資金だけで挑むと、資金繰りに苦しみ、せっかくのチャンスを逃すケースが目立ちます。
「現場では忙しすぎて制度のことまで手が回らない」
現場監督や後継者候補の立場からすれば、さらに切実です。
- 日々の現場管理で手一杯
- 法改正や補助金の情報が専門用語ばかりで理解しにくい
- 申請書類は分厚くて専門家でないと読み切れない
その結果、せっかくの制度や支援策が「知らない」「使えない」まま終わってしまうのです。
こうした「現場の困りごと」と「制度の壁」のギャップを埋めることこそ、これからの建設業に必要な実務支援のテーマです。
補助金・建設業許可・経審をどう理解すれば武器になるのか
2026年度の新しい流れ
環境省が概算要求に盛り込んだ 「防災拠点への再エネ導入支援50億円」 は、単なる環境対策にとどまりません。
避難施設や公共施設の整備は 防災・減災事業 としても発注され、地元の建設会社にとって新しい仕事のチャンスになります。
さらに、住宅の脱炭素化支援(ZEH化や省エネ診断など)、自然公園施設の長寿命化、太陽光パネル廃棄対策など、今後の予算には「建設業と関わらざるを得ないテーマ」が次々と登場しています。
補助金と建設業許可の関係
「補助金=メーカーや施主がもらうもの」と思われがちですが、実際は施工を担う建設会社の名前や実績も審査対象になるケースがあります。
つまり、建設業許可がないと補助金申請の事業者登録に参加できないこともあるのです。
また、許可業種を広げておくことで、補助金を活用する工事の範囲も広がります。
例えば…
- 電気工事業を追加すれば太陽光設備工事に対応できる
- 管工事業があれば省エネ設備の導入工事も受注可能
経営事項審査(経審)の役割
公共工事を狙うなら 経審は“避けて通れない関門” です。
経審は点数制ですが、次のような要素が評価されます。
- 自己資本や利益率などの財務状況
- 技術者の資格や人数
- 過去の工事実績
ここで点数を上げておけば、補助金案件の施工体制証明にもプラスに働きますし、金融機関からの評価も上がります。
資金調達とのつながり
制度融資や銀行借入でも、「建設業許可」「経審の点数」「補助金の採択実績」は信頼度を示す材料になります。
「許可がある」「経審で客観的な評価がある」「補助金で国の後押しを受けている」
この3点がそろえば、資金調達のハードルは大きく下がります。
つまり、国の補助金・許可・経審はそれぞれ別物ではなく、相互にリンクして会社の実力を見える化する仕組み。
ここを理解しておくことが、今後の受注拡大や資金繰り改善につながります。
今日から始められる3つのアクション
1. 自社の「許可業種」を棚卸しする
まず取り組みやすいのは、自社が保有している建設業許可を改めて確認することです。
「とりあえず一番メインの業種だけで取ったまま」になっていないでしょうか?
たとえば――
- 太陽光発電設備の工事 → 電気工事業
- 省エネ配管や空調機器の導入 → 管工事業
- 蓄電池を含むリフォーム → 建築工事業+電気工事業
補助金や脱炭素関連の事業に関わるには、業種追加が大きな武器になります。
許可業種の見直し・追加申請は、将来の仕事の幅を広げる第一歩です。
2. 経審の点数アップを戦略的に進める
「経審は大手のためのもの」と思われがちですが、中小企業でも対策は可能です。
具体的には――
- 決算書を経審対策型に整える(利益計上や自己資本比率を改善)
- 技術者資格を計画的に取得させる
- 実績をこまめに登録し、評価対象を漏らさない
数十点アップするだけで、参加できる工事の幅が広がることもあります。
3. 補助金の情報収集をルーティン化する
補助金はタイミングを逃すと1年間待たされることもあります。
経営者一人で追いかけるのは大変ですが、次の方法で負担を減らせます。
- 商工会議所や自治体の補助金メール配信を登録
- 建設業に強い専門家(行政書士・中小企業診断士など)に伴走してもらう
- 自社内で「補助金担当」を置いてチェックを習慣化
「いざチャンスが来た時にすぐ動ける体制」を作っておけば、資金繰りの不安を減らせます。
この3つを同時に完璧にやる必要はありません。
しかし、小さな一歩を積み重ねることで、会社の体力と信用は確実に高まります。
補助金・許可・経審を味方にして次の一歩へ
建設業界を取り巻く環境は、災害対策や脱炭素といった新しいテーマで大きく動いています。
今回の「公共施設の再エネ導入に50億円」というニュースは、その象徴的な一例にすぎません。
中小の建設会社にとっても、補助金や制度を上手に活用すれば――
- 新しい分野の工事に参入できる
- 経審の点数アップで公共工事の門戸が開く
- 銀行や自治体からの信用が高まる
こうしたプラスの循環を生み出すことができます。
「うちは小さいから関係ない」と思ってしまうのはもったいないこと。
むしろ地元に根差した中小企業だからこそ、防災拠点や公共施設の整備に関わる意義があります。
まずは自社の建設業許可を見直し、経審や補助金の情報にアンテナを立てることから始めましょう。
もし制度の理解や申請準備に不安があるときは、建設業に精通した行政書士などの専門家に相談するのも有効です。
一歩先を見据えた経営のために
建設業許可・経営事項審査・補助金活用は、どれも「攻め」と「守り」を兼ね備えた経営ツールです。
この3つをしっかりと押さえておけば、目先の工事だけでなく、数年先を見据えた経営基盤づくりにつながります。
次の入札や補助金募集が始まる前に、今日からできることを一つでも動かしてみてください。
それが未来の仕事と資金調達のチャンスを広げる、確実な一歩になるはずです。