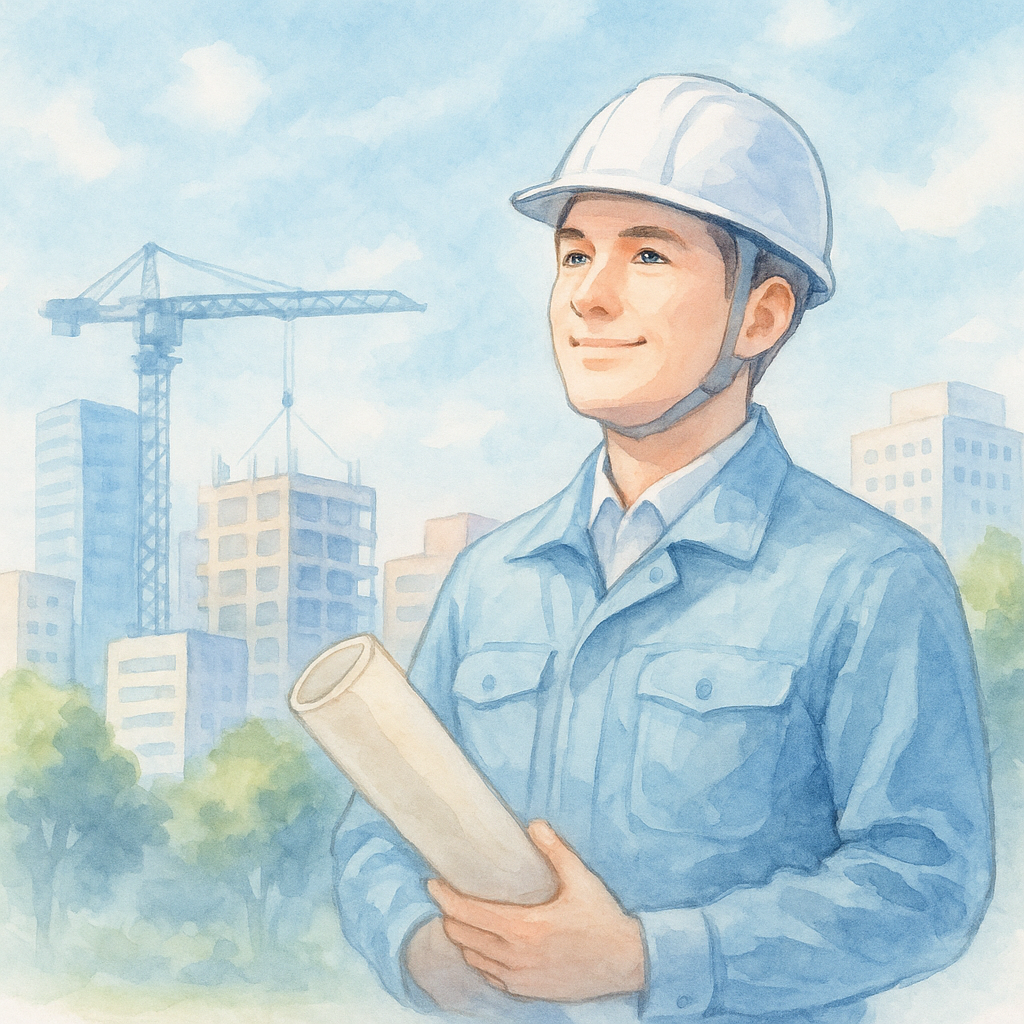目次
「人が足りない」だけじゃない。現場が抱える“見えない不安”
「人が足りないんだよ、うちも。」
この言葉を、建設業に関わる方から聞かない日はないほど、いまや「人手不足」は業界共通の悩みになっています。職人の高齢化、若年層の入職減、現場作業の敬遠――こうした要因が重なり、技能者の数は年々減り続けています。
けれど、ただ人数が減っているだけではありません。
現場ではそれ以上に、“未来が見えないことへの不安”がじわじわと広がっているのではないでしょうか。
- 「経営事項審査(経審)ってうちにも関係ある?」
- 「これからも許可を維持できるだろうか…」
- 「外国人材の受け入れって、結局どうしたらいいの?」
制度は変わり、評価軸も変わり、技術や人材のあり方も激変していく中で、日々の仕事に追われながら、こうした“モヤモヤ”を放置している事業者さんも少なくありません。
実際、日建連(日本建設業連合会)の発表によると、2035年には技能者が129万人分不足すると推計されています。これは建設業全体の約3分の1にあたるインパクトです。
このまま「何とかなるだろう」と手を打たずにいると、気づいたときには公共工事の入札にも参加できず、助成制度も活用できず、気力も資金も尽きる――そんな“ゆるやかな衰退”に陥るリスクすらあります。
でも、逆に言えば「今この10年でどう備えるか」が、次の10年の明暗を分けるのです。
次章では、実際に今、現場の経営者たちが直面している「実務的な困りごと」と、そこにある制度的な“ギャップ”について具体的に掘り下げていきます。
制度と現場の“ズレ”が招く落とし穴とは?
「うちは建設業許可も経審も関係ないから…」
そう思っていた経営者が、ある日突然、元請からこう言われたとします。
「今回は公共工事だから、経審点数がないと仕事お願いできないんですよね…」
これ、実は珍しくない話です。
下請けでも元請けでも、許可や経営事項審査(経審)の状況が“取引の条件”になるケースは今後ますます増えていきます。とくに資本金3,000万円未満・従業員20人以下といった中小事業者こそ、「制度に乗り遅れるリスク」が大きいのです。
📌 なぜ「制度のズレ」が現場を困らせるのか?
背景には、制度の見直しスピードに現場の理解が追いついていないという構造的な課題があります。
たとえば――
- 建設業法改正で労務費の適切な支払いが義務化されたのに、「何を根拠に計算すればいいのか分からない」。
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録が推奨されているのに、「操作が面倒で現場が止まる」と敬遠される。
- 経審での加点要素がどんどん増えているのに、「点数の仕組み自体が理解されていない」。
こうした“理解の乖離”が、結果として現場の選択肢を狭めてしまっています。
👷 実際にあったこんな声
- 「経審って名前は聞いたことあるけど、点数って何をどうやって決まるの?」
- 「CCUSは登録したけど、現場でどう使うのか結局分からずそのまま」
- 「監督署から“労務費補正を反映して”って言われても、設計単価と実際の支払いに差があるのが現実」
こうした“制度疲れ”の声は、特に従業員10人以下の小規模事業者から多く聞かれます。現場に向き合う時間を削って、複雑な書類や制度に対応しなければならない――この負担感が、新しい取り組みを敬遠させてしまうのです。
けれど、この状況を「無理だ」と諦める必要はありません。
次章では、「複雑に見える制度をどう味方につけるか」を、具体的な対処法を交えて紹介します。
建設業許可、経審、CCUS、労務費補正…それぞれの制度はバラバラに見えて、実は“ある視点”で整理することで一気に理解が深まります。
複雑な制度も“つなげて考えれば”味方になる
「許可はあるけど、経審はよく分からない」
「経審はやってるけど、CCUSまでは手が回らない」
「制度が多すぎて、何がどこにつながるのか見えない」
こうした声に共通しているのは、「制度を“別々のもの”として捉えてしまっている」という点です。けれど実は、これらは1本の線でつながっているのです。
📌 制度の全体像は「許可 → 評価 → 加点 → 受注」の流れ
たとえば、公共工事を安定的に受注する企業になるには、以下のような“制度の流れ”を理解しておく必要があります。
| 項目 | 目的 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 法的に建設業を営む資格 | 500万円以上の工事には必須/更新忘れ注意 |
| 経営事項審査(経審) | 会社の経営力・技術力を“点数化” | 点数で公共工事の入札参加可否が決まる |
| CCUS | 技能者の職歴・資格・経験をデータ化 | 加点対象になる/雇用安定にも直結 |
| 労務費補正対応 | 適正な人件費の反映 | 未対応だと賃上げ分が価格に転嫁されない |
| 就労環境整備(週休2日など) | 若手・外国人材に選ばれる業界へ | 経審・助成制度でも加点される可能性 |
すべては「より良い条件で仕事を受けられる会社になる」ための仕組みです。
🛠 制度は“先手”で動いた者勝ち
たとえば…
- CCUSのレベル別評価に対応していれば、経審の技術力点数がアップ。
- 労務費補正を理解し、きちんと支払っていれば、元請との契約交渉でも信頼度が上がる。
- 経審の点数を“見える化”しておけば、元請の公共案件に呼ばれる確率が上がる。
つまり、制度は複雑に見えても「点」で見るから混乱するのです。
「線」でつなげて、“会社の未来地図”として活用すれば武器になるのです。
今すぐできる、制度活用のはじめの一歩とは?
「制度が大事なのはわかる。でも、結局どこから手をつければいいの?」
そんな声に、私はこう答えるようにしています。
「まずは“許可の棚卸し”と“経審の可視化”から始めましょう」
✅ ステップ①:建設業許可の“状態”をチェック
最初の一歩は、意外にも「基本の確認」です。以下、ぜひチェックしてみてください。
- □ 現在の許可業種は最新の事業内容と合っていますか?
- □ 更新や変更届、期限切れになっていませんか?
- □ 専任技術者や経管の条件は維持できていますか?
許可の更新忘れや要件未達は、最悪の場合、許可の取り消しや入札除外にもつながります。制度活用どころか「土俵に立てなくなる」リスクがあるため、まずは許可状況の“棚卸し”が大切です。
✅ ステップ②:経審点数の“見える化”
次に、経営事項審査(経審)の点数。これは「受注力を数字で見せるツール」です。
中小事業者でも、こんな工夫で点数アップが狙えます。
| 対策 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 財務体質の改善 | 借入金の圧縮/自己資本比率の向上 | 経営状況点アップ |
| 技術者の育成・登録 | 技術職員のCCUS登録/資格取得支援 | 技術力点アップ |
| 労働環境の整備 | 週休2日・残業削減/社会保険加入率向上 | 労働福祉点アップ |
| 退職金共済加入 | 建退共掛金の充実 | 福利厚生加点・離職率抑制 |
| 外国人材の計画的活用 | 言語研修やキャリア支援の導入 | 将来の加点対策+安定雇用 |
行政書士などの専門家に相談すれば、経審点数のシミュレーションも可能です。
「制度を使って、いくらの公共工事に挑めるか」を見える形にすると、経営の地図が一気にクリアになります。
✅ ステップ③:小さく始めて“制度に慣れる”
すべて一度に整備しようとすると、正直、挫折します。
だからこそ、最初は「できそうなところから、少しずつ」進めるのがコツです。
- 技能者1名だけでもCCUSに登録してみる
- 建退共の掛金を月数千円だけ増やしてみる
- 自社の経審点数をまず「知る」ところから始める
小さな行動の積み重ねが、「制度に強い会社」をつくります。
10年後を変えるのは「制度」より、あなたの“決断”かもしれない
技能者が129万人足りなくなる――
この数字は確かに衝撃的です。でも、本当に怖いのは「人がいないこと」ではなく、
「何もしないまま、取り残されてしまうこと」
かもしれません。
未来の現場を支えるのは、“今の一手”の積み重ね
建設業界はこれから、デジタル化・自動化・外国人材活用といった大きな変革期に入っていきます。制度もどんどんアップデートされ、現場の働き方も様変わりしていくでしょう。
けれど、そうした変化の波に流されるのではなく、「選ぶ側」であることが大切です。
- うちはこの業種で勝負していく
- 技術者をこう育てていく
- 制度をこう活用して、地域に根を張る
その選択をするのは、誰でもない「あなた自身」です。
💡 制度を使いこなす会社は、未来に強い
建設業許可や経審、CCUS、助成制度…
これらはすべて、「小さな会社でも、持続的に成長できるように」と用意された“共通言語”です。
制度に強くなることで――
- 元請や発注者からの信頼が高まる
- 安定的な受注につながる
- 若手や外国人材にも選ばれる職場になる
そうした“選ばれる会社”になることで、10年後も必要とされる存在であり続けられるのです。
🌱 一歩を踏み出すあなたへ
もし「うちもそろそろ動き出さなきゃ」と思われたら、
まずは“話してみる”ことから始めてみませんか。
許可の見直しや経審の点数アップ、制度の使い方について――
現場に即したアドバイスをくれる専門家もいます。
私自身、現場を理解した立場から、建設業者さんの制度活用をサポートしています(行政書士としての支援も承ります)。
「難しそう」だからこそ、一緒に取り組む価値があります。
あなたの会社の“10年後の景色”を変えるお手伝いができたらうれしいです。