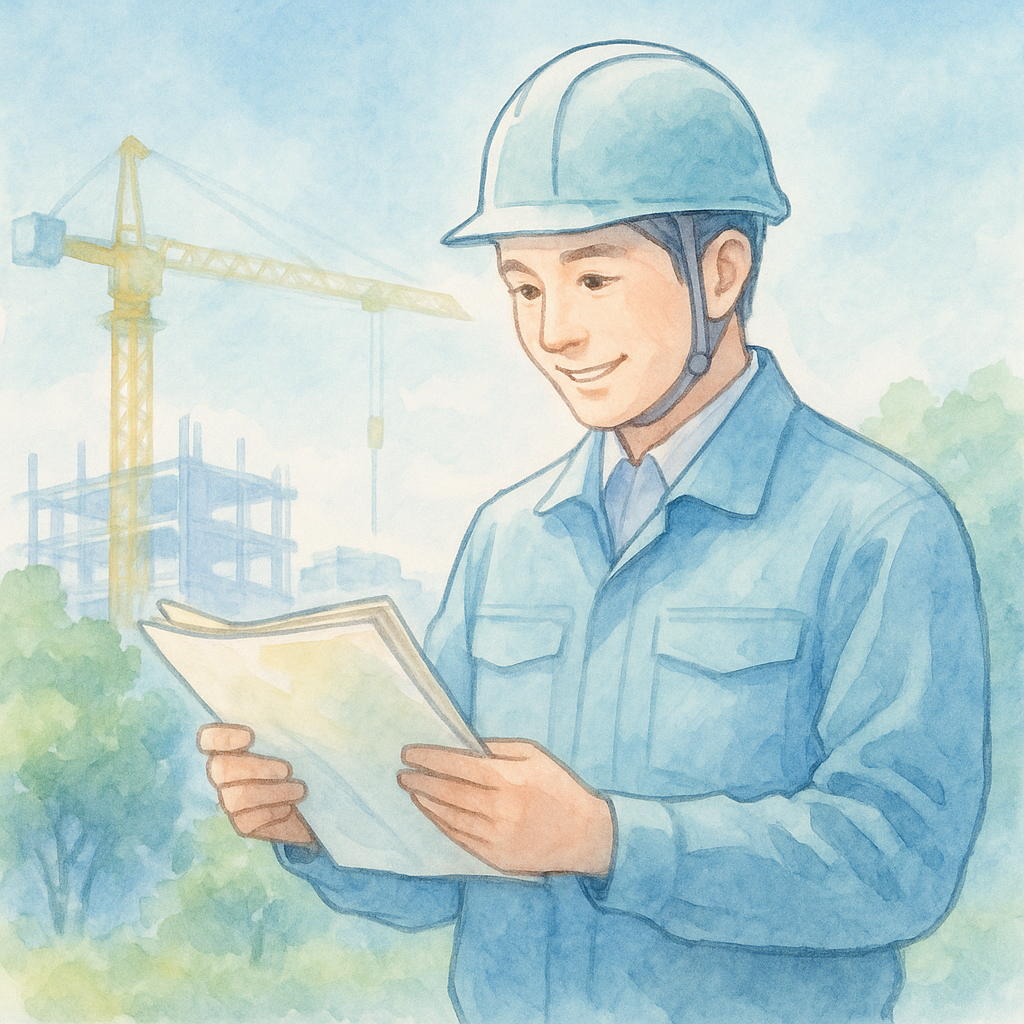目次
「人が足りない」は他人事じゃない──公共工事の現場で起きていること
「入札の時期は読めても、発注者の事情までは読めない」
こんな声を、建設業に携わる方から耳にすることがあります。
実は今、自治体側でも大きな問題が起きています。
国土交通省の調査によると、都道府県や政令市の7割以上が「職員だけでは公共工事の発注事務をこなせない」と回答。特に「設計・積算」や「監督・検査」では約8割が限界を感じており、実際に多くの自治体が外部委託に頼っているのが現状です。
これ、単なるお役所の話じゃありません。
自治体の手が回らなければ、工事の発注も遅れ、スムーズな着工にも影響が出ます。
現場で「なかなか案件が動かないな」と感じたとき、その裏には、発注者側の“人手不足”があるかもしれません。
小規模自治体では、土木・建築の技術職員が一人もいないところもあります。
そんな中で、設計や積算、監理といった専門性の高い業務をこなすのは至難の業。必然的に外部の専門家に委託せざるを得ないわけです。
つまり、建設業者と行政は、表裏一体のパートナー関係になってきている。
発注する側も、受注する側も、「人が足りない」「制度が複雑」「仕事が進まない」──
そんな悩みを抱えながら、なんとか現場を回しているのが現実です。
こうした状況のなかで、私たちのように「制度を読み解く実務家」が果たせる役割も、少しずつ変わってきました。
次章では、実際に「どの業務が外注されているのか」「なぜそうなったのか」を、現場に近い声とともに掘り下げていきます。
技術職ゼロの自治体も?現場に響く“見えない遅れ”の正体
「発注者が設計を出してこない」
「予定通りに現場が動かない」
「何度も変更や中断が入る」
こうした現場の声は、必ずしも建設業者側の問題ではありません。
背景には、自治体側の“見えない苦労”があることをご存じでしょうか。
国土交通省の最新調査では、都道府県・政令市の71.6%が「職員だけでは業務が難しい」と回答しています。
特に深刻なのが、以下の分野です。
- 設計・積算(79.1%)
- 監督・検査(74.6%)
たとえば三重県では「中堅・若手職員の層が薄い」との声があり、札幌市では「再発注の増加による精査業務の負担」が問題に。さらに、兵庫県では「積算に時間がかかりすぎて監理業務に手が回らない」といった声も。
つまり、「書類が遅い」「動きが遅い」と感じる場面の多くは、担当者が不在だったり、一人で複数業務を掛け持ちしていたりと、現場の“人”の限界が原因なのです。
地方に行くほど状況は深刻です。
人口10万人未満の市の8%、町の35%、村の72%で、土木・建築技師が一人もいないという衝撃的な実態があります。
こうなると、設計・積算・照査・監督・品質確保といった高度な判断を要する業務を、経験の浅い事務職員だけで対応している自治体も少なくないのです。
一方で、外部の建設コンサルに委託しても、成果物の質にはバラつきがあるという問題も。
大阪府のように「誰に頼むかで品質が変わってしまう」という課題を抱える自治体も多くあります。
つまり、建設業の現場では、知らず知らずのうちに「人手不足の波」を受けているのです。
自治体と現場がうまく連携できなければ、見えない遅れや手戻りが積み重なり、
最終的には現場の工期遅延やコスト増加にもつながりかねません。
次章では、こうした状況を踏まえ、「制度として今どうなっているのか」「どこまで外注が認められているのか」など、制度面をわかりやすく解説していきます。
どこまで外注できる?公共工事の発注業務と委託のルール
建設業の現場にじわじわ影響を及ぼしている、自治体の「外注依存」。
ここで気になるのが、「そもそもどこまで外部に任せていいのか?」という制度上の枠組みです。
実は、公共工事の発注にかかる業務には、いくつかの段階とルールがあります。
📌 発注関係事務は大きく分けて5つ
- 入札・契約
- 設計・積算
- 技術審査・品質確保
- 監督・検査
- 発注体制全体の調整
このうち、「設計・積算」「監督・検査」などの技術系業務は、以前から外部委託が行われてきました。
根拠となるのは、地方自治法や会計規則に基づく「業務委託契約」です。
ただし、すべてが自由に外注できるわけではありません。
発注者(自治体)には、以下のような“責任と判断”が常に求められます。
- 最終的な契約決定権は自治体が持つ
- 外注先が作成した設計や積算内容を、発注者が理解し説明できる必要がある
- 成果物の検査・受領・評価を職員側が行う必要がある
つまり、委託=丸投げOKではなく、あくまで職員の補助的な位置づけ。
「技術的な裏付けが弱い」「人が足りない」からといっても、委託内容を精査し、判断する体制は不可欠です。
📊 グラフが示す“現実的な委託率”
国交省の調査によれば、次のような傾向が明らかになっています。
| 業務内容 | 外部委託をしている割合(グラフより推定) |
|---|---|
| 設計・積算 | 約80%以上 |
| 監督・検査 | 約70%以上 |
| 技術審査・品質確保 | 約60%程度 |
| 入札・契約 | 約30%未満 |
とくに「設計・積算」は、可能な限り外部委託している自治体が多数派。
一方で「入札・契約」は、法的な制約が大きいため、今でも多くの自治体が職員対応にとどめています。
さらに最近では、公益法人や建設コンサルだけでなく、広域連携や一部事務組合での共同処理も進んでいます。
たとえば、小規模自治体では「技術職ゼロ」を補うため、隣接する自治体と共同で発注事務を行うケースも。
これらの制度設計は、「建設業者にとっても見逃せない情報」です。
なぜなら、受注側にとっても──
発注元の体制や委託先によって、契約までのスピードや書類の質に差が出るからです。
次章では、こうした制度の理解をもとに、建設業者として「どんな備えや工夫ができるか」、実務的な行動提案をお届けします。
発注の“詰まり”にどう備える?建設業者ができる3つの実務対策
自治体の人手不足や発注業務の外注化は、もはや一部の例外ではありません。
では、私たち建設業者側はどう備えるべきなのでしょうか?
発注の遅れや手戻りに振り回されず、安定した受注と施工を目指すために、今すぐできる実務対策を3つご紹介します。
✅ 1.「相手の都合」を見越したスケジューリング
設計・積算の準備が遅れがちな今、発注者側のリズムに合わせたスケジュール設計が必要です。
たとえば…
- 「年度後半(1~3月)は発注が詰まりやすい」
- 「設計・仕様変更は委託先との調整で時間がかかる」
といった“発注側の事情”を踏まえたうえで、工程の見直しや工事時期の提案を行うと、信頼を得やすくなります。
✅ 2.「書類の不備ゼロ」を目指すプロ体制
発注者側が外注先との連携に苦労している今、受注側の提出書類が整っているかどうかが、ますます重要になっています。
- 積算根拠や数量根拠の説明資料
- 工期変更にともなう計画変更書
- 書式や提出順序の統一
こうした基本的な整備こそが、発注担当者の負担を減らし、結果的に「次の案件も頼みたい」と思わせる要因になります。
✅ 3. 専門家との連携で「制度の抜け」を防ぐ
委託の範囲が広がる中、「あれ、これ誰に確認すればいいんだ?」という制度上の“抜け”が発生することもあります。
たとえば、経営事項審査(経審)の時期に提出が間に合わなかった、補助金に必要な書類が整っていなかった…といった事例もよく見られます。
そんなとき頼りになるのが、制度と現場を橋渡しできる外部パートナーです。
たとえば、補助金・経審・建設業許可の手続きに明るい行政書士や、資金調達支援を含めたサポートができる実務家に、早めに相談するのが得策です。
💡ひとことアドバイス
「現場で起きている小さなズレ」こそ、早期に気づいた人が得をする時代です。
「なんか最近、役所の動きが遅いな」
「前より発注書類の精度が低くなってる?」
そんな違和感があったら、実務の中で“察知”し、社内や外部と連携することで先回りできるようになります。
まずは、目の前の“小さな気づき”から。建設業と制度のスキマを埋めよう
建設業の世界では、「現場に出ればすべてがわかる」と言われることがあります。
けれど今の時代、現場の“外”で起きていることが、仕事の進み方に大きく影響してくる──そんな時代に変わってきています。
設計・積算・監督・検査──
これまで発注者が担ってきた業務の多くが、外部委託に移行しつつあります。
けれど、委託先の事情までは見えづらく、実務のすれ違いや行き違いも増えています。
そんな中で私たち建設業者ができることは、「備える」ことと「気づく」こと。
- 発注者の“動きが遅い”理由に気づく
- 書類の精度や提出のタイミングに気を配る
- 外部専門家とゆるやかにつながっておく
これだけで、現場がスムーズに進む確率はぐっと上がります。
補助金や経営事項審査のタイミングを逃さないことも、
来年の入札に向けて「今のうちに」整えておくことも、
実はすべて“段取り八分”の世界。
もし、「こんなとき、どうすればいいんだろう?」と感じる場面があれば──
制度の隙間や、役所のしくみの“裏側”を読み解く専門家に、気軽に声をかけてみてください。
私たち実務支援の現場では、「制度と現場の橋渡し」をすることが何よりの役割だと感じています。
建設業の未来は、「現場力」だけでなく、「制度理解力」でも変わる時代。
ほんの少し先を見据えた準備が、1年後・3年後の大きな差になります。