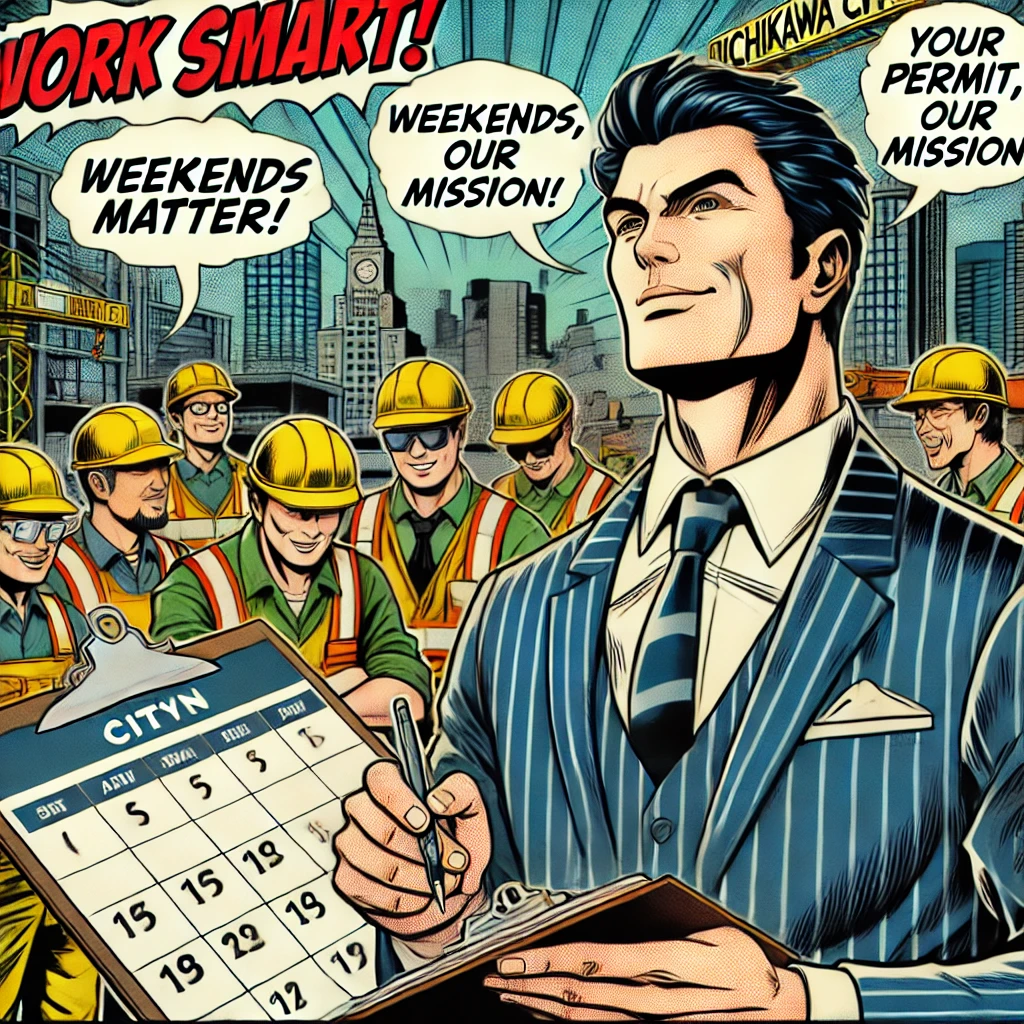「週休二日って、ウチの業界じゃ無理だよな……」
そんな声を、現場で何度も耳にしてきました。
千葉県市川市を拠点に、建設業に特化した行政書士として活動している私のもとには、日々さまざまな悩みや課題が寄せられます。特にここ最近、関心が高まっているのが――「完全週休二日制」の試行導入に関する話題です。
2025年度、国土交通省は直轄の営繕工事において“完全週休二日”の試行を本格化させ、現場管理費にも補正が加わる新たな制度設計をスタートします。一見、働く人の健康や家族との時間を守る「良い制度」にも思えますが、現場のリアルはそう簡単ではありません。
- 工期が延びる?
- 人件費が増える?
- 曜日指定の制約で現場が回らない?
- 曜日調整したのに補正係数が減額される?
――結局、負担だけが増えるんじゃないの?と感じる経営者・職人さんも多いのが実情です。
でも、そんな時こそ、制度の“裏側”と“使い方”を知ることがカギになります。
そしてその“橋渡し”ができるのが、私たち行政書士の仕事です。
この記事では、市川市を拠点とする私・松野芳賢が、「完全週休二日制」の動向と建設業の現場に与える影響、そして地域密着で支援できる行政書士としての具体的なアドバイスを、専門性と現場目線の両方から解説します。
建設業界の今とこれからを、少しだけ前向きに考えてみませんか?
目次
「休めって言われても…」建設業の現場で起きているジレンマ
建設業界で働く方々にとって、「週休二日制」と聞いても、正直ピンとこないという方が多いかもしれません。
特に中小の工務店や下請企業が多い市川市内では、次のような現場の声が頻繁に聞かれます。
- 「人手が足りないのに、どうやって土日を休みにするの?」
- 「現場が止まれば収入も止まる。補正係数でほんとに補えるの?」
- 「元請のスケジュール次第で、休めるかどうかなんて決められない」
こうした現実を知れば知るほど、「制度」と「現場」の間にある深い溝を感じざるを得ません。
市川市の建設業者さんから聞いた“本音”
ある市川市内の中堅解体業者の社長は、こんな悩みを語ってくれました。
「土日を原則休みにしろって言われても、ウチの現場は都内。しかも平日は騒音規制で作業時間が限られるから、土日こそ稼ぎ時なんだよね。制度の趣旨は理解できるけど、現場の事情までは見えてない気がするなあ」
また、別の塗装業者さんからは、
「日給月給で働いている職人も多いから、休みが増えると収入が減る。それで職人が離れちゃったら、会社も成り立たないよ」
という切実な声も。
大手と中小、都市と地域で「制度格差」が広がる?
こうした背景もあり、「完全週休二日」をめぐる取り組みには、元請と下請の格差や都市部と地方の事情の違いといった、複雑な課題が絡んできます。
制度導入に前向きな会社でも、補正係数の適用や現場閉所日の設定について、発注者との協議がうまくいかなければ、逆に「減点評価」のリスクすらあるのが現実です。
市川市内でも、「制度は知っているけど、どう対応すればいいかわからない」という声が少なくありません。
でも、だからこそ。
こうした混乱や不安を軽減する“調整役”として、行政書士が現場に入る意味があるのです。
「完全週休二日」の制度、どう変わる?行政書士がやさしく解説
建設業界で進む“週休二日制”の推進。
でも実は、その背景には法律や制度の改正が関係しています。
ここでは、行政書士の視点から「どんな制度で、どう対応すればいいのか」を、できるだけやさしく整理してみます。
まず、制度の基本を押さえよう
2025年度からスタートする「完全週休二日制」の試行は、国土交通省の直轄営繕事業の新築工事(=Ⅰ型)が対象です。
この制度のポイントは、以下の通り
- 原則すべての週で「土日を休日」とすることを義務化
- 週休2日が守られた場合、労務費と現場管理費に補正係数(1.02/1.01)が加わる
- 実際の閉所日が少なければ補正係数は減額される(=成果連動型)
これまでの制度では「労務費のみ」補正されていたのに対し、今回は現場管理費(経費)まで補正対象になる点が大きな違いです。
一方で、「新築以外の工事(=Ⅱ型)」の場合は月単位で4週8休を確保すれば労務費に1.02の補正が入るだけで、現場管理費は対象外です。
📌 補正係数とは?
これは国が発注時に工事費の見積もりを調整するための係数で、「週休二日を実現してくれたら、コスト上乗せOKですよ」という仕組みです。
現場ごとに調整が必要になる「協議制」
もうひとつ重要なのが、「事前協議」の必要性です。
受注業者は、着工前に発注者(=国)と「本当に土日が休めるのか」を協議しなければなりません。
たとえば、以下のような事情があれば土日をずらすことも可能です。
- 現場が土日にしか作業できない(住宅街などの規制)
- 天候リスクを避けたい工種がある(外構・屋根など)
- 関係業者の都合で曜日調整が必要になる
ただし、平日に代休を設定するなど、週に2日以上の閉所は“必須”です。
行政書士としては、こうした協議の準備段階で、
- 工期延長の合理性をどう説明するか
- 曜日変更の正当性をどう示すか
- 管理費・人件費の見積根拠をどう書類化するか
といった「根拠づけ」の支援ができます。
評価制度も要注意!“減点リスク”に備えよう
制度をうまく使いこなせれば評価は上がりますが、「形式だけ整えて実態がともなわない場合」には、減点の対象にもなります。
評価のポイント
- 「工事成績評定」で週休2日の取組が反映される
- 月次・週次で閉所状況の確認が必要(書類活用)
- 閉所実績が不十分だと、補正係数が減額される可能性あり
そのため、記録の取り方や文書の整備にも注意が必要です。
「制度は怖くない」――建設業者が前に進むために、今できること
働き方改革、完全週休二日制、補正係数……。
どれも聞くだけで難しく感じてしまう制度ですが、実際の現場では、「知らない」ことが一番のリスクになります。
建設業界は今、制度と現場の間に挟まれ、さまざまな調整が求められています。
でもだからこそ、制度を理解し、味方につけた事業者は強いのです。
💡では、今すぐできる一歩は?
- 自社が制度の対象になり得るかどうか、契約書や仕様書を確認してみましょう
- 発注者との協議や書類準備に不安がある場合は、行政書士に相談してみましょう
- 補助金やBCP対策と連動させ、経営全体を見直すチャンスと捉えてみましょう
💬「制度のこと、相談してよかった」と思ってもらえる存在へ
私は千葉県市川市を拠点に、建設業許可や補助金支援、BCP対策などに専門特化した行政書士として活動しています。
現場のリアルな悩みに寄り添いながら、行政と民間の“橋渡し”として、「実際に役立つ制度対応」を支援しています。
- 制度を使いたいけど、どこから手をつけていいかわからない
- 発注者との協議をサポートしてほしい
- 評価対策や補助金申請も合わせて相談したい
そんな時は、ぜひ一度ご相談ください。
市川の建設業界を、もっと元気にしたい。
そんな思いを胸に、私はこれからも現場に寄り添い、地域と共に歩んでいきます。
「制度を活かす力」が、地域建設業の未来を変える。
一緒に、その第一歩を踏み出しましょう。