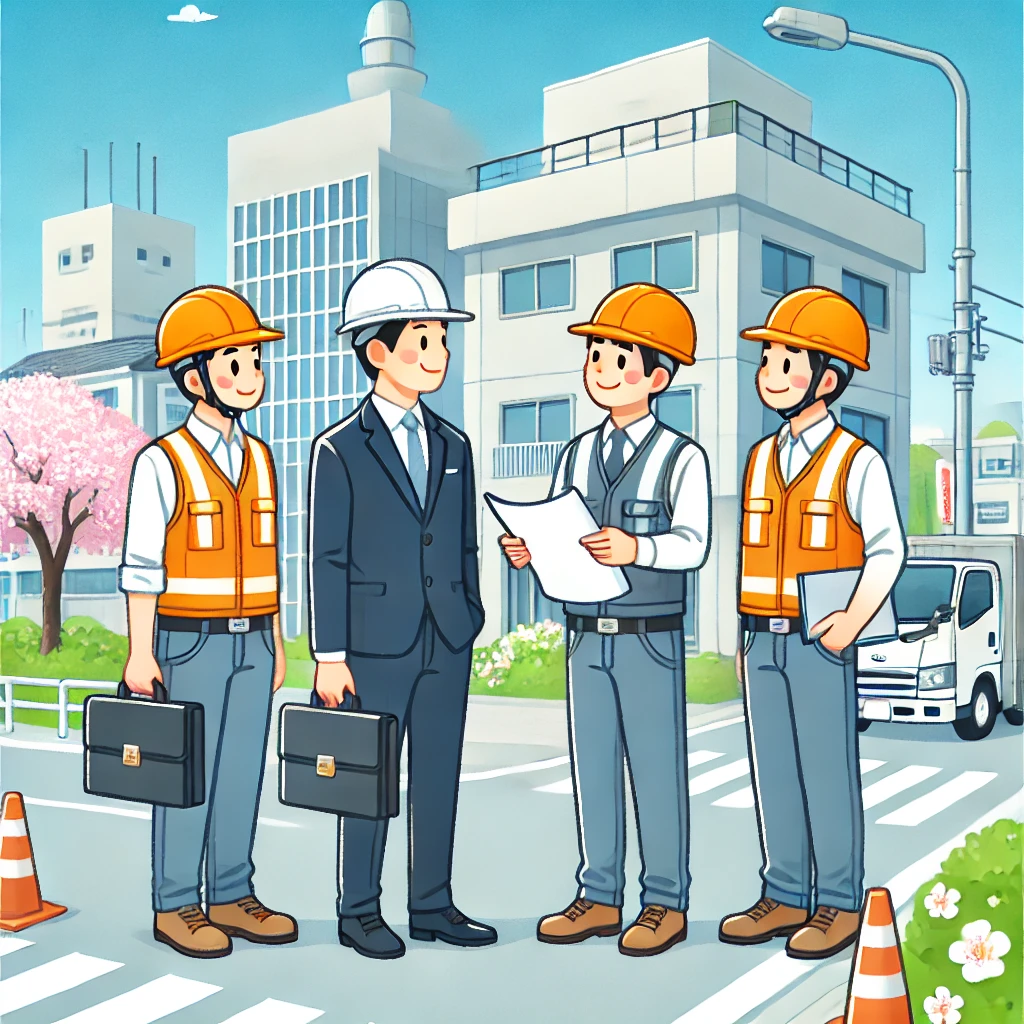目次
行政書士が語る、市川の建設業に今必要なサポートとは
「最近、見積りの金額が合わなくて困ってる」
「どうしても赤字ギリギリになってしまう」
こんな声を、市川市の中小建設業者の方からよく耳にします。
特に、市や町レベルの公共工事では、国の標準歩掛をそのまま使って予定価格を設定してしまい、現場の実態とズレてしまうケースが後を絶ちません。
でも、安心してください。
国土交通省は2025年度から、自治体独自の歩掛(ぶがかり)設定を後押しする調査と好事例の水平展開を始めます。つまり、地域に合ったコスト構造で発注価格を見直す流れが、いよいよ本格化するということ。
これは、市川市のような中小企業が多い地域の建設業者にとって大きなチャンスです。
なぜなら、「うちはロットが小さいから」「うち程度の規模じゃ相手にされない」といったあきらめが、制度的にも払拭されようとしているからです。
そして、こうした制度の変化をいち早くキャッチし、現場に届けるのが、私たち行政書士の役割でもあります。
特に建設業許可や入札、補助金サポートに関わっている行政書士は、現場の声と制度の橋渡し役として地域経済を支える立場にあります。
次章では、実際に市川市でどんな現場課題があるのか、リアルな声を交えて紹介していきます。
「自分たちも何かできるかも」と思ってもらえるきっかけになれば嬉しいです。
現場の声が届かない──小さな建設業者が抱える“理不尽”
うちは市の工事を受けたけど、手間賃が出ないんです
市川市で外構工事業を営むある社長は、こう漏らしました。
「図面通りにやったのに、設計金額から“勝手に”差し引かれたんですよ。なんでも“歩切り”だって…」
この「歩切り(ぶぎり)」という言葉、現場ではもう何年も前から問題になっているものです。
正式な根拠なく発注者が予定価格から金額を引く行為で、業界では“暗黙のルール”のように扱われてきました。
ですが2021年には国交省が全国調査を実施し、品確法違反(公共工事の品質確保の促進に関する法律)として廃止を徹底するよう通達を出しています。
ところが、実際にはまだまだ残っている。
特に市区町村レベルの発注において、「歩切り」や「標準歩掛のそのまま流用」が横行しており、それが中小の建設業者の利益を圧迫しています。
「工事の半分は人件費。けど、それが評価されない」
たとえば、舗装工事や小規模な改修工事などでは、段取りや地域特有の気候・地形に合わせた対応が必要です。
でも、国が設定した標準歩掛は「大ロット・標準条件」で計算されているため、市川のような住宅密集地での細かな手間が反映されないのです。
市川市で住宅地中心に塗装業を営む別の経営者もこう話します。
「ペンキ一斗缶を持ってハシゴを何回も往復する手間、あれって時間も体力も取られるんです。でも見積りに出せない。まして役所の発注だと“これが標準です”って言われて終わりです。」
こうした声は、表に出にくいけれど、現場では確実に存在しています。
次章では、こうした問題に対して行政書士がどう関わっていけるのか──
最新の国交省の動きや制度変更も踏まえて、専門家の立場からわかりやすく解説していきます。
行政書士が読み解く「歩掛」「歩切り」の仕組みと、最新の制度動向
「歩掛」って結局、何のためにあるの?
まず基本からおさらいしておきましょう。
「歩掛(ぶがかり)」とは、工事を行うのに必要な労働力・機械・材料などの標準的な量を示した“作業単価の根拠”のことです。
例えば「1㎡あたりの塗装に、何人で何時間かかるか」「どんな機材を何台使うか」といった“見積りの基準”を構成する要素です。
行政が発注する公共工事では、これをもとに予定価格を設定するのが基本です。
ところが──
「歩切り」はなぜ問題なのか?
「歩掛」によって正当に積算されたはずの金額から、発注者が恣意的に金額を差し引くこと。これがいわゆる「歩切り(ぶぎり)」です。
- 「今回は簡単な現場だから」と金額を引く
- 「他社と比べて高いから」と根拠なく減額する
- 「予算の都合」で無理やり金額を下げる
こういった行為は、発注者側の勝手な裁量で価格が下がってしまうため、現場の健全な運営が難しくなります。
実はこの「歩切り」、品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)違反とされ、2021年に国が全自治体に調査・是正を求めた問題でもあります。
最新ニュース:国交省が「独自歩掛」の実態調査へ
2025年度、国交省は地方自治体が独自に歩掛を設定しているかを調査し、優良事例を全国に展開する方針を打ち出しました。
- 小規模工事に対応した地域特有の歩掛を把握
- 市区町村でも現場に合った予定価格を設定できるよう支援
- 同時に「歩切り」の再調査と是正を徹底
つまりこれからは、「国の標準に従うだけ」の時代ではなくなり、地域ごとの実態に合わせた価格設定が求められる時代へとシフトしていくということです。
行政書士としては、この制度の背景を理解した上で、こうした動きに的確に対応するためのアドバイスや書類作成支援を行うことが求められます。
行政書士は何ができる?
- 建設業許可・経営事項審査などにおける「実績の適正評価」をサポート
- 入札・契約に関する書類チェックとアドバイス
- 補助金や融資の際に必要な「積算の妥当性」を文書化
これらはすべて、“現場の声を制度に反映させる”ための大切なステップです。
次章では、行政書士としての具体的な行動提案──
「明日からできること」にフォーカスした実用的なアドバイスをお届けします。
明日からできる!建設業者が“行政書士と一緒にできる”3つの対策
「制度は動いている。でも、自分たちはどう動くべきか?」
歩掛や歩切りといった公共工事の予定価格に関わる課題は、まさに今、変革のときを迎えています。
しかし、どんなに制度が改善されても、「現場の声を届ける行動」や「自社の体制づくり」を始めなければ、何も変わりません。
そこで今回は、行政書士としての実務経験をもとに、市川市の建設業者が“明日からできること”を3つに絞って提案します。
✅1. まずは「自社の積算根拠」を記録・整理しておく
歩切りや見積り不一致の被害にあっても、「どの作業にどれだけ手間がかかったか」を示せなければ、主張が通りません。
行政に提出する書類だけでなく、普段の工事ごとに“見えないコスト”をメモしておくだけでも、立派な証拠になります。
記録すべき項目の例
- 搬入・搬出の回数や距離
- 養生や段取りにかかる時間
- 地元特有の気候・地形による追加作業
- 近隣対応・工程調整の負担 など
これらの情報は、行政書士が積算の根拠資料や意見書を作成する際に非常に役立ちます。
✅2. 行政書士との定期的な「業務レビュー」を始める
公共工事や入札参加の準備だけでなく、
- 「実績がうまく評価されていない」
- 「入札でどうも競争に勝てない」
という悩みも、実は“書類の質”や“制度理解の深さ”で差が出ているケースが多いです。
毎月でなくてもOKです。
年に1〜2回のチェックでも、補助金・融資・入札の精度が格段に上がることは珍しくありません。
松野行政書士事務所では、こうした「建設業のための顧問契約(段階制)」も用意しています。
中小事業者に合わせた初期費用を抑えた設計になっており、「とりあえず相談してみる」という選択肢が現実的です。
✅3. 市川市の制度に関する意見は“声を届けるだけで価値がある”
国交省が進める今回の調査でも、「建設業者からのヒアリング」が含まれています。
つまり、あなたの声が国の制度に反映される可能性があるということ。
地元で困っていること、理不尽だと感じていることがあれば、行政書士を通じて制度に届けるルートがあるんです。
行政書士には、相談者の声を制度や文書に“翻訳”する力があります。
今こそ、「どうせ変わらない」と諦めず、一緒に“変えていく”行動を選んでみませんか?
地域と共に進む建設業の未来へ──“声を上げる”ことから始めよう
「建設業の未来は、自分たちの手で変えられる」
市川市のように中小建設業者が多数を占める地域では、「声が届かない」「仕組みが合っていない」と感じることも多いでしょう。
でも今、国交省が動き出し、歩掛の実態調査や歩切りの是正を通じて、“地域に合わせた価格設定”の土壌が整い始めています。
つまり、今こそ“変わるタイミング”。
そしてこの変化をチャンスにできるかどうかは、「情報をつかんで、動けるかどうか」にかかっています。
行政書士は、まさにそのサポート役です。
許認可や経営事項審査、融資申請や入札書類の作成支援──
複雑な制度と現場のギャップを埋め、「言葉にできない現場の声」を文書で伝える役割があります。
「気軽に相談する」から、すべては始まります
「まだ許可を取っていないけど…」
「細かい積算の話はしたことがない…」
そんな方こそ、まずは一度話してみてください。
事務所は市川市東国分。地元密着で、あなたの声をしっかり受け止めます。
🌱ご相談の一歩が、地域建設業の未来を変えるかもしれません。
まずは「話してみようかな」と思っていただけたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。