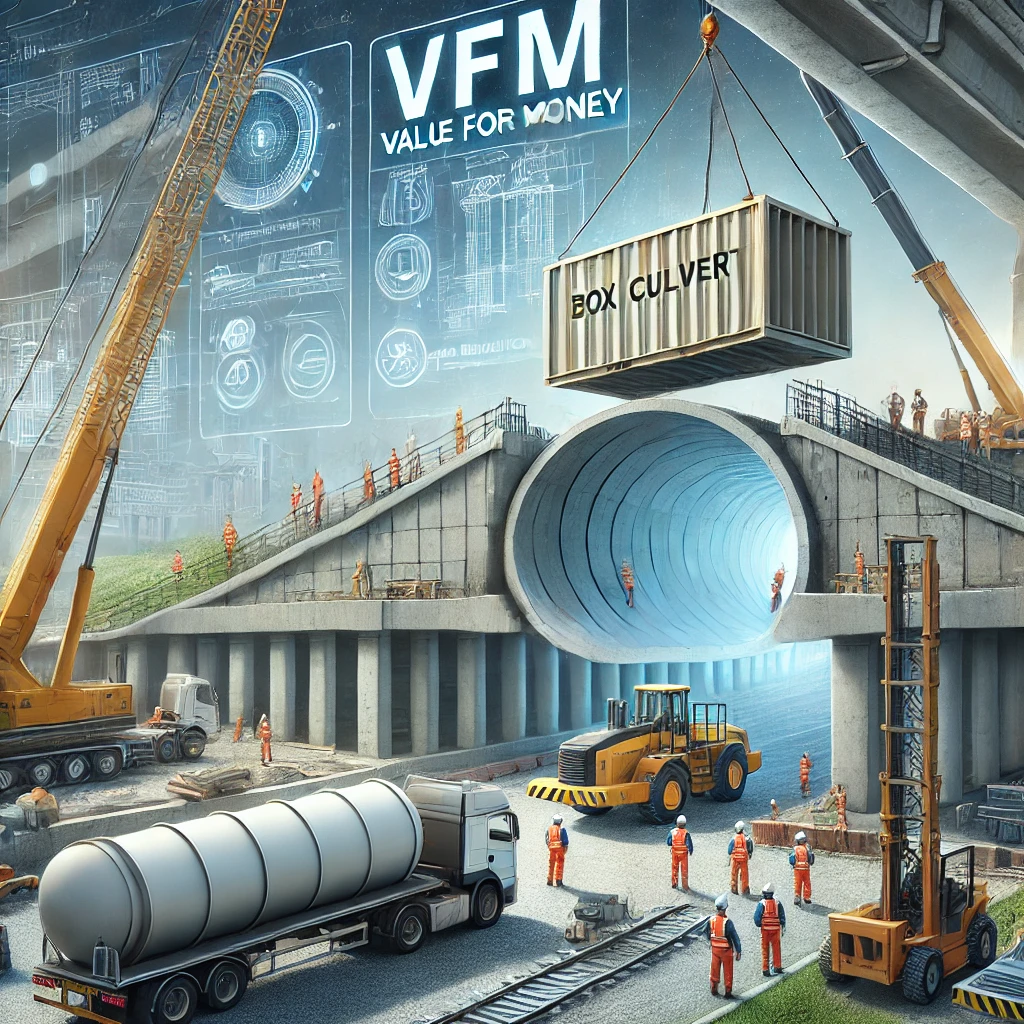建設現場の課題とVFMの可能性
あなたは、現場打ちとプレキャスト製品のコスト差で悩んだことはありませんか?
「プレキャストは便利だけど、価格が高い…」そんなジレンマを感じている建設業関係者も多いでしょう。
国土交通省は大型ボックスカルバート(函渠)において、コスト以外の総合的な価値(VFM:Value for Money)を導入し、現場打ちとプレキャスト製品の比較を進めています。
この記事を読むと…
✅VFMの仕組みと評価基準がわかる
✅2025年度以降の標準化の流れを把握できる
✅建設業者にとってのメリット・注意点を理解できる
現場の効率化を目指しつつ、経営者が知っておくべき戦略を解説していきます!
VFM導入の背景と課題
プレキャストvs現場打ち:コストだけでは決められない時代に
建設業界では、「プレキャスト製品は高いが、工期短縮ができる」「現場打ちは安いが、手間と時間がかかる」というジレンマが長年続いてきました。
例えば、市川市内のある現場では…
「プレキャストの大型ボックスカルバートを導入すれば、工期を1カ月短縮できるが、コストが現場打ちよりも高くなる…。経営的にはどちらが得なのか?」
このように、コストだけでは判断しづらい場面が多発しています。
VFM導入の背景:単なるコスト比較から価値比較へ
国土交通省は、2023年度に「VFM(Value for Money)」という新しい評価基準の検討を開始しました。VFMは以下の多角的な観点から評価されます:
✅効果性:目標達成度や品質への寄与度
✅効率性:投入資源に対する成果の比率
✅経済性:ライフサイクルコスト(LCC)全体の最適化
✅公平性:多様なステークホルダーへの配慮
✅持続可能性:環境や社会への長期的影響
こうした指標を使い、2024年度には新規設計で試行検証が行われる予定です。今後の実績データの蓄積と評価基準の確立が期待されています。
建設業界のリアルな課題
1️⃣「本当にVFMが高いのか?」の判断基準がまだ曖昧
2️⃣発注者・受注者ともにVFM評価に慣れていない
3️⃣35㎡以上の大型函渠ではコストのばらつきが大きい
特に、大規模な現場では様々な要素が複雑に絡み合うため、VFM評価の数値化と標準化には時間がかかる可能性があります。現時点では個別案件ごとに慎重な検討が必要です。
🏢行政書士が解説!VFMと建設業の未来
建設業界のVFM(Value for Money)導入は、単なるコスト比較から「価値の最大化」へと評価基準が変わる潜在的な転換点です。しかし、現場では「VFMって結局どういう仕組み?」「行政手続きへの影響は?」と疑問に感じる方も多いでしょう。
ここでは、行政書士の視点からVFMの基本、建設業許可・入札への可能性のある影響、今後の方向性についてわかりやすく解説します。なお、以下の内容は現時点での情報に基づく予測であり、実際の政策や運用によって変わる可能性があることをご了承ください。
📌VFMとは?行政手続きとの関係
VFM(Value for Money)は、単なる「最安値」ではなく、コストに対して得られる価値を総合的に評価する考え方です。
✅ライフサイクルコスト(LCC):建設後の維持管理・修繕費も含めた評価
✅省人化効果:人工数の削減による生産性向上
✅環境負荷の低減:CO2排出量削減などの持続可能性
公共工事では、このような総合的な価値評価により「単価が高くてもVFMで評価される可能性」があります。ただし、具体的な評価基準や重み付けは個々のプロジェクトの特性や目的によって大きく異なり、現時点では確立された標準はありません。
📌建設業許可・入札への影響の可能性
🏗1.建設業許可の審査基準への影響
VFMの導入によって、受注者側にも新たな対応が求められる可能性があります。
将来的には、経営事項審査(経審)の評価項目にVFM関連の指標が追加される可能性も考えられますが、これはあくまで推測の域を出ません。現時点では、国土交通省から具体的な発表はなく、今後の政策動向を注視する必要があります。
➡当面の対応策:建設業の動向を見守りつつ、「総合的な価値提供」を意識した事業計画を検討する
📑2.入札制度における可能性
これまでの入札では「価格の安さ」が重要視されていましたが、VFM導入によって「環境配慮」「施工の効率性」なども評価される可能性があります。
💡予想される変化(ただし現時点では確定していません)
✔総合評価方式の入札でVFMの考え方が反映される可能性
✔ライフサイクルコストの視点が重視される傾向
➡当面の対応策:総合評価方式の入札において、工期短縮や環境配慮など多角的な価値を示すデータを準備しておく
📌これからの建設業界で求められること
1️⃣プレキャストと現場打ちの両方の特性と適用条件の理解
2️⃣個々のプロジェクト特性に応じた最適な工法選択の検討
3️⃣行政書士と連携し、最新の政策動向を踏まえた経営計画の検討
国土交通省は2025年度にVFMの評価手法を本格的に導入する方針ですが、実際の運用や効果については今後の展開を見守る必要があります。急激な変化よりも段階的な移行が予想されるため、バランスの取れた対応が重要です。
💡プロジェクトの総合的な価値を高める具体的なアプローチ
VFM(Value for Money)の概念を活用することで、建設業者は単なるコスト競争から「価値提供」へと視点を変えることができます。ただし、具体的な評価基準はまだ確立されていないため、以下の提案はあくまで参考にとどめ、個々のプロジェクト特性に応じた検討が必要です。
🏗1.プレキャストと現場打ちの適材適所の検討
プロジェクトの特性によって、プレキャストが有利な場合と現場打ちが有利な場合があります。
✅工期短縮が重要な場合:プレキャストが検討対象になる可能性
✅人手不足の現場:省人化効果の高いプレキャストが検討対象になる可能性
✅施工条件が複雑な場合:現場打ちの柔軟性が評価される可能性
💡実践のヒント
✔設計段階から複数の工法を比較検討する
✔現場条件とプロジェクト目標に合わせて最適な工法を選択する
✔施工計画書に選択理由と期待される効果を明記する
📑2.ライフサイクルコスト(LCC)視点の導入
短期的なコストだけでなく、長期的な視点での検討が重要になる可能性があります。
例えば…
🏗現場打ちの場合:「初期コストは低い傾向があるが、個々の施工品質によって維持管理コストが変動する可能性」
🏗プレキャストの場合:「初期コストは高い傾向があるが、品質管理された環境で製造されるため耐久性に期待できる可能性」
💡検討の視点
✅材料・工法の耐久性データの収集
✅維持管理計画も含めた総合的な提案
✅長期的なコスト予測の提示
♻3.環境配慮の視点を取り入れる
環境負荷の低減(CO2排出量削減)も今後重視される可能性があります。
✅検討できる対策
✔エコ建材や低炭素コンクリートの採用可能性の検討
✔施工の省エネ化(重機の効率的運用など)
✔工法によるCO2排出量の比較検討
特に自治体や国の発注工事では「環境配慮」が評価される傾向が強まる可能性があり、
今後の競争力強化のためにも環境対策の検討が重要になるかもしれません。
📌プロジェクトの総合的な価値を高めるために
✅プロジェクト特性に応じた工法選択
✅ライフサイクルコスト(LCC)の視点を取り入れる
✅環境配慮の可能性を検討する
建設業界では、今後「ただ安いだけの工事」より「総合的な価値を生み出す工事」が求められる可能性が高まっています。
今後の動向を見据えた準備
📌この記事のポイントをおさらい
🔹VFM(Value for Money)は効果性、効率性、経済性、公平性、持続可能性など多角的な観点から総合的な価値を評価する考え方です
🔹プレキャストと現場打ちはそれぞれ特性が異なり、プロジェクトごとに最適な選択は変わります
🔹ライフサイクルコスト(LCC)の視点を取り入れることで、長期的な価値の検討が可能になります
🔹環境配慮の視点も今後重要性が増す可能性があります
国土交通省は2025年度に、VFMの評価手法を本格的に導入する方針ですが、具体的な運用方法や評価基準はまだ確立されていません。今後の動向を注視しながら、柔軟に対応していくことが重要です。
💡建設業者が検討できること
✅1.自社のプロジェクトを多角的な視点で評価する習慣をつける
👉単純なコスト比較だけでなく、工期、品質、環境影響などを総合的に検討する
✅2.提案書や計画書に複数の価値要素を明記する
👉工期、品質、安全性、環境配慮など多角的な視点を盛り込む
✅3.行政書士など専門家と連携し、最新の政策動向を把握する
👉変化する評価基準に柔軟に対応できる体制を整える
📢価値を意識した時代へ!段階的な準備を
今後の公共工事は「最安値を競う時代」から「価値を提供する時代」へ徐々にシフトしていく可能性があります。
ただし、この変化は一夜にして起こるものではなく、段階的な移行が予想されます。過度な期待や性急な対応ではなく、バランスの取れた準備と柔軟な対応が建設業の未来を切り拓くカギとなるでしょう。
👉VFM導入の詳細や建設業許可の取得について、行政書士に相談したい方はお気軽にご連絡ください!🚀
※本記事の内容は2025年3月現在の情報に基づいており、今後の政策動向や実際の運用によって変わる可能性があります。最新情報については関係機関への確認をお勧めします。